
|
家永三郎教授の声明
私はここ一〇年余りの間、社会科日本史教科書の著者として、教科書検定がいかに不法なものであるか、いくたびも身をもって味わってまいりましたが、昭和三八・九両年度の検定にいたっては、もはやがまんできないほどの極端な段階に達したと考えざるをえなくなりましたので、法律に訴えて正義の回復をはかるためにあえてこの訴訟を起こすことを決意いたしました。憲法・教育基本法をふみにじり、国民の意識から平和主義・民主主義の精神を摘みとろうとする現在の検定の実態に対し、あの悲惨な体験を経てきた日本人の一人としてもだまってこれをみのがすわけにはいきません。裁判所の公正なる判断によって、現行検定が教育行政の正当なわくを超えた違法の権力行使であることの明らかにされること、この訴訟において原告としての私の求めるところは、ただこの一点に尽きます。
昭和四〇年六月十二日
家永三郎
|

|
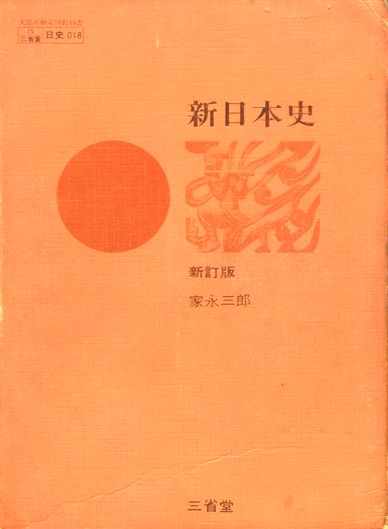
|
この訴訟が起こされたとき、「教育大学新聞」はその訴状全文を掲載した特集号を刊行したが(昭和40年7月25日付第437号)、この特集号には、全国各地の書店・団体などから注文が相次ぎ、新聞の増刷が必要となって、この時ばかりは「教育大学新聞」は一時的に全国紙になったかのような様相を呈した。(通常はブランケットであるが、本特集号はタブロイド版12ページ。左写真参照。)
このような家永氏の行動をもって、彼が何か「左翼」であるかのように誤解している人が多く、また、権力側のジャーナリズムも意図的にそのような宣伝をしている節がある。しかしながら、彼のために一言しておくならば、彼は決して「左翼」というような学者ではない。頑固な民主主義者、頑固な平和主義者、現代の自由民権論者とでもいうべき思想の持ち主である。権力悪を憎む気持ちが強いのは事実だと思うが、だからといって社会主義者や共産主義者であるわけではない。彼の学問的関心も、そもそもは古代史(それも仏教思想や倭絵)の学者であり、その後近代史の研究に比重を移したが、主として自由民権運動などの、自由主義者、民主主義者の思想的研究にあり、その方法論も「実証主義」と言うべきものでいわゆる「唯物史観」とは縁もゆかりもないものである。
彼の教科書(左写真は昭和40年版表紙)にしても、権力側が主張するような「左翼的」なものではない。記紀についての記述も津田左右吉的なもので、とやかく言うようなものではない。教科書は限られたスペースで要点を書かなければいけないから、記述がある程度断定的になるのはやむをえないことである。家永氏の教科書に限らず、あらゆる角度から見て完璧な教科書などというものはなく、どのように良くできた教科書であっても、その気になりさえすれば、いくらでもケチは付けられるものである。「訴状」に見られる検定の実態は、最初からケチ付けの意図をもって臨んだ「言いがかり」、「いやがらせ」という印象が強く、当局は権力をかさにイジメモードに入っていたように見える。彼らは一見するとおとなしそうでひ弱そうな家永氏を見くびっていたのではないだろうか。実は結構芯の強いところがあるのだ。
戦後日本においては、左翼運動が、平和主義運動、民主主義運動として展開されてきた面があり、その点から、外見的に彼の行動が左翼的に見えるのであろう。しかし、類似は外見だけである。そもそも、左翼思想の持ち主であれば、自分の主張を裁判に訴えるようなことはしないだろう。左翼的思考からすれば、裁判所は国家権力の一機関にすぎず、それに期待するのはナンセンスということになるからだ。左翼が裁判闘争をやるのは起訴されてやむをえずというのが普通で、自分から訴訟を起こしたりはしない。ところが、彼は民主主義者なのであって、裁判所や法秩序というものにかなりの期待を持っていたわけである。この訴訟も権力の濫用防止が主旨であって、「階級闘争」を考えているわけではない。訴訟を支援する者に左翼知識人が多いことは事実だが、本人が左翼であるわけではない。彼を「左翼」とするのは、為にする宣伝か、または純然たる勘違いのどちらかである。
もっとも、権力にとっては、本来の「左翼」よりも彼のような人物の方が、なまじ同じ土俵の上で勝負してくる分だけ、かえって扱いにくい、ということはあるだろう。
わが国の支配政党は自由主義と民主主義を看板にしているのだから(羊頭を掲げて狗肉を売っているとも言えるが)、熱烈な自由主義者、民主主義者である家永氏のような人物を自らのイデオローグに迎えるくらいの度量の広さがあってもよさそうなものだが、そうはならないのが日本の不幸なところである。
彼の訴訟がその後の教科書検定に与えた影響は大なるものがあるが、頑固一徹も社会に貢献できる見本のようなものだ。
| 訃報・家永三郎氏は2002年11月29日89歳で永眠されました。謹んで哀悼の意を表します。 |