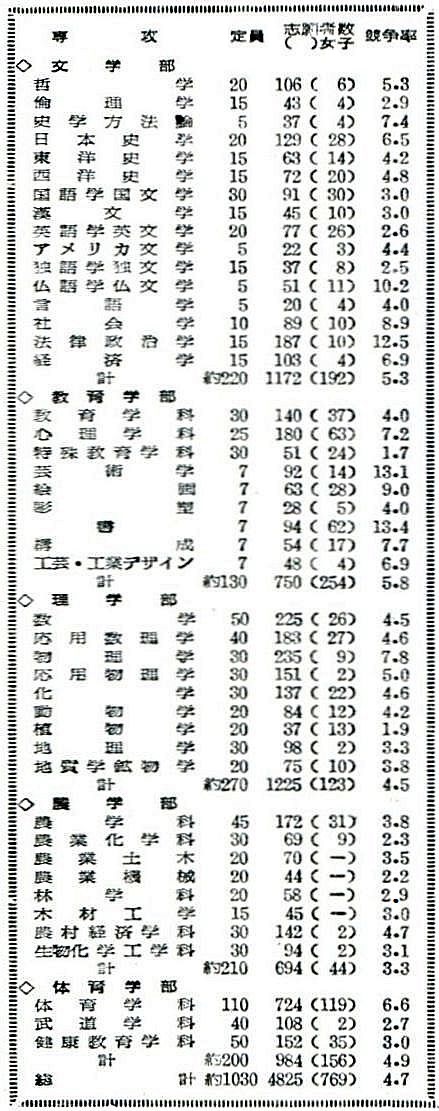学部選択 | 文学部 | 教育学部 | 理学部 | 農学部 | 体育学部 |
| Faculties | Human Science | Educational Studies | Natural Science | Agricultural Science | Sports Studies |
文学部は充実している点では日本でも有数といわれる。だが筑波問題の渦の一つの中心ともなって、教授層の全き分裂、学長による教授会の“教育の道具視”、権限縮小、無視はさらに、教育大廃校、新生文学部からの反対派教官パージをも予想させる。教育研究への権力の露骨な介入である筑波、その過程での学内の中央集権化に反対した教授会の今後の姿勢がその将来を決定する。と同時にそれは、全国学園闘争の中で投げかけられた「教育研究することの意味」が尖端的に問われたのであり、社会と、生きることの意味を常に問う文学部の学問内容の必然だったろう。文学部は少人数で密度の高い学習で君を鍛え、さらにその学問の意味をも君に問いかけるだろう。
| 哲学 (Philosophy) 科学哲学は異色の講座 |
哲学、哲学史、科学哲学の3講座から哲学教室はできている。本学哲学教室の特色は科学哲学であり、講座として独立しているのは本学のみである。これは「現代科学の成立基礎と構造を解明し、その矛盾欠陥を指摘する機能をもつ独立した一つの科学」ということで、一時はこの教室が科学哲学界の総本山的様相を呈した時代もあったというが、今はあまりふるわない。日本における科学哲学不振に比べ、米国などでは科学論理学、科学史に各大学とも力をそそいでいるといわれ日本では未開の学問ともいえる。科学哲学では認識論の高木勘弌助教授、哲学講座は自然哲学で数理を中心にライプニッツ等を研究する永井博助教授、認識論の小川弘助教授、哲学史ではヘーゲル研究の宮本冨士雄教授、ギリシア哲学の村治能就教授がスタッフである。
哲学の学生といってもむずかしい顔で人生を思索する、といったタイプもなく、それぞれ自由に動き回り、クラスのまとまりは欠けた方のようだ。学生運動に打ちこむ者、スポーツサークルをやる者、そしてどこにも顔をみせず勉強をしているらしい者、このわけのわからぬのが哲学たるゆえん?
卒論はニーチェ、マックス・ウェーバー、初期マルクス、ヘーゲル、ベルグソン――等々多彩である。ついでに留年の多いのもこのクラスの特徴、哲学をきわめるのに四年では不足というわけか。
女子の進出が目ざましい文学部でも哲学科はまだ少ない方で毎年2人くらいなので、女子学生の健闘が期待されるとか。
| 倫理学 (Ethics) 広く社会経済の学習も |
倫理学というので、さぞや堅いところであろうと思い、人倫の道を実践しようという心掛けを持って毎年新入りがやってくる。しかし半年もたたぬうちにその先入観は無残に打ち砕かれるだろう。日本の倫理学は特に、体制従属を上から強制する修身的側面が強く、敗戦のショックはあったものの、現実の人間生活の場からの倫理学は未だに発達していない。本学もその例外ではなく、戦前の反革命イデオロギーの中枢といった面影はなくなったにしても、多くは古来先哲の解釈学を主としている。
一昨年来の学園闘争においては「人間疎外」がいく度か叫ばれたにもかかわらず、この科の先生方はその間そろって耳の具合が悪かったらしく、沈黙を守っておられた。倫理とは実践の学という側面が強いはずだが、と思われるのだが、諸先生は「筑波新大学」に夢がふくらんで、はたの小わっぱの声は耳に入らぬらしい。
学生はあらゆることにマジメで、反戦闘争からサークル、自治会まで幅広く活躍している。ただ、師弟関係はうまくないようだ。
教官は、歴史哲学、実存主義研究の大島康正、ドイツ批判哲学の小牧治、古代中世倫理思想史の渡部正一、仏教倫理の川那部保、ギリシャ思想の堀田彰、中国倫理思想史の高橋進と全領域をカヴァーしている。
| 史学方法論 (Historical Methodology) 人類学としての発展 |
研究室前の廊下に山と積まれた考古学標本は文学部にあって特異である。大きく民俗学、考古学の2講座からなり、全国でも数少ない講座学科として、学問的にも学界をリードしている。
民俗学は柳田国男を継承するもので日本史の和歌森、桜井教官の応援をうけてすぐれた研究業績をあげている。教官は民間信仰伝承を専攻する直江広治教授、社会伝承、特に家族制度を研究している竹田亘助教授がいる。
考古学は東洋史的な広範囲の研究を行い、外書講読もある。教官は旧台北大学在任中以来、シナ海沿岸地域の文化交流を研究している国分直一教授、中国からオリエントにかけての広範な研究をしている増田精一助教授がいる。
ともあれ教育大アカデミズムを代表する専攻であるだけに、学生数も5人という少人数で、独特の雰囲気をかもし出している。
| 日本史学 (Japanese History) 注目される教科書裁判 |
古代・中世・近世・近代の4講座を有し、教育大文学部を代表する有名専攻であるとともに、学問的にも日本史学界の指導的地位を保ち続けている。
古代では和歌森太郎教授が、民俗学の成果を摂取して民衆の生活史を再現することを追求し、桜井徳太郎助教授は古代宗教信仰史に民俗学的方法を用いながら挑んでいる。中世の芳賀幸四郎教授は、禅林文化の研究に独自の観点をもって取り組んでいる。
近世の西山松之助教授は文化史が専攻で、江戸時代の町人生活、家元制度の研究で成果を上げている。津田秀夫助教授は社会経済史の開拓者で、民衆の立場から幕藩体制社会の論理構造を解明しておられる。
近代では家永三郎教授が思想史の分野を開拓し、自由民権運動の思想家の研究のほか、古代仏教思想にも造詣が深い。また同教授の「太平洋戦争史論」は人気を集めている。大江志乃夫助教授は、明治維新史では若手のホープと目され、家永教授と共に人民の歴史意識の国家統制に強く抗議している。
家永教授は歴史教育を歪曲する権力の「教科書検定」に対し、国を相手に訴訟を起こし、教官、学生一体の応援をうけて、市民運動に力を注いでいる。こうした状況から、学生は社会の中で歴史をどうとらえるかという意識をもって反戦闘争に力を入れる者が多く、筑波闘争においても先進的部分を輩出した。
| 東洋史学 (Oriental History) 中国史研究が中心 |
中国文化大革命、ベトナム戦争、朝鮮動乱等、世界の注目をあびる東洋を研究する学問でありながらこの教室の教授先生方はひっそりと、現代には目を閉じておられるようだ。
講座は中国古代、中世、近代と中国史のみであり、守備範囲は狭いが、中国史では東大と一、二を争うアカデミックな城となっている。教授陣は中世社会経済史の中島敏教授、古代社会経済史の木村正雄教授、中世文化思想史の酒井忠夫教授、および近代政治史の田中正美助教授、岡本敬二助教授とガッチリを固まっており、学界をリードしている。しかし現代史は講義がない。
一年生から史料講読という見慣れぬ漢字でしぼられ、学生はよく勉強しているが、アカデミズムにあきたらず、独自に毛沢東を研究する者や、反戦運動に首をつっこんで、帰ってこなかった男もいる。一方教授諸先生はいずれおとらぬ移転推進派のつわ者で、文学部教授会からも学生からも孤立しているが「筑波移転のあかつきには」と怪気炎をあげておられる。
このいささか分裂気味のクラスがまたそれなりの面白さを生みだし、特異な雰囲気を持っている。卒論は、先生方の熱意にもかかわらず、中国革命に人気が集中し、ここでも「断絶」を感じさせる。
就職は教職が多いが、最近は各県ともダブついているので苦戦しており、かといってジャーナリズムには向かず、出版界あたりにおさまるものが増えている。
| 西洋史学 (Western History) 学問と社会と自己と |
マジメで貧乏、その上ヤボというのが教大生のトレード・マークであるが、この教室はそういう点では教育大らしくない教室であろう。史学科の中では女性の比率が最も高く、比較的可愛い娘が多いという噂がある。しかしこの教室からは戦闘的女子学生を生みだし、勇名をはせた。
古代・中世・近代の3講座にわかれているが、杉勇教授の退官のため、定員不足のままになっている。古代にはローマ史、特にキリスト教のローマ帝国流布についての権威であるクリスチャンの弓削達助教授、中世には思想史に明るい兼岩正夫教授とイタリア史の清水広一郎講師、近世にはフランス革命を中心とする18世紀政治史の穂積重行教授がおられる。その他ギリシャ史、古代オリエント史、現代ヨーロッパ史等は非常勤講師を頼んでいる。
日本においては洋学コンプレックスというのか、一般に西欧からの輸入学問が主流をしめてきたため、哲学、社会科学など、マルクス、ウェーバーをやるにも西洋史の知識なくしてはできないため、西洋史はいわば他の諸科学にひきずられて発展してきたともいえる。なにしろ歴史の舞台から遠いため史料不足の悩みはあるが、最近になって西洋史がそれ自体、独立した学問となってきたのが注目される。
筑波闘争においては学生、教官共々先進的部分(?)を形成し、教官がすべて移転反対派の論客であるため、学生はのびのびと実践的学問に精を出している。教官は穂積教官をはじめ、学生問題に理解がある。
| 国語学国文学 (Japanese Language and Classics) 実証的国語研究 |
英文とならぶ、総勢120余名の大教室である。学風は京都に近いということで、評論よりも実証的な訓注釈を重んじ、そのためか受験界には特に重きをなしている先生が多い。
大きく国語学と国文学に分かれる。国語学には万葉集・古事記を中心とした国語学の権威、中田祝夫教授、音韻学・説話文学の馬淵和夫助教授、中世語・国語学史の小松英雄教授の三氏がいる。国文学には中世文学、特に和歌史・歌論史に造詣が深く、歌人でもある峯村文人教授、上代・中世文学の小西甚一教授、平安文学、特に源氏物語に造詣が深く、受験生にはなじみの深い鈴木一雄助教授、近世、特に俳文学の尾形仂助教授、中世、特に徒然草・擬古物語の桑原博史助教授、現代文学専攻で詩人の分銅惇作助教授の6氏がいる。昨年まで柳樽拾遺演習で人気を博していた吉田精一教授が東大専任になられたので現在はすべて文理大出身者が教授を構成することになった。
近年、女性の進出がすさまじく、闘争そっちのけで、彼女とうまくやっていた御仁もいて、文学科の他の専攻同様、なごやかな空気がただよっている。女性の多いクラスはノンポリが多いというジンクスはここにも生きている。
卒論は、これだけ古文の教官がそろっているにもかかわらず、約半数は現代文学で、小林秀雄のほか、吉本隆明、椎名麟三、宮本百合子等も対象に上っている。
堅い講義の多い教育大でも、国文は羽目をはずして気軽に聞けるので、他専攻から息抜きにもぐりこむ学生が多い。また三年になると奈良・京都の名所旧跡をたずねる旅行があり、その他小グループの研究会ももたれている。「言語と文芸」は、この教室の研究誌である。
| 漢文学 (Chinese Classics) 新たなる胎動期に |
漢文学は、経子学、中国言語学、漢文学の3講座から成っている。経子学講座は中国古代哲学、特に尚書学に造詣の深い小林信明教授、中世哲学研究の今井宇三郎助教授。中国言語学講座は、中国文法論をもっぱら研究している牛島徳次教授、中国文学専攻で漢六朝史の鈴木修次助教授。漢文学講座では中国哲学、特に春秋学研究の鎌田正教授、中国言語学の松本昭助教授、近世詩の横山伊勢雄講師と陣容が整っている。
学生は一年から、史料講読にしぼられてよく勉強するのが多いそうだ。歴史の古い中国を対象にするために、卒論は老子、孟子から魯迅・現代文学と多様な領域にわたる。中国哲学・文学・語学・日本漢文と漢文の領域全体を必修として漢文の全領域にわたって深い学習がなされる。クラス活動はミンセイ系が完全掌握し、新入生にサークル指導もこれに入れ、あれに入るな等と党派主義的にやったとか。
日本の文化史は中国からの移入に始まったともいえ、それ以後強い影響を与えてきた。このための漢文は時に「修身」の形で政治支配に利用されたきらいもあるが大きな学問分野としてあった。だが中国との国交途絶もあり、どちらかというと日陰に追われた感じがなくもない。
卒業生は大学院進学がかなり多いが、就職は国語教師が主である。
| 英語学英文学 (English Language and Literature) 文学部一の女性天国 |
他大学同様、この教室も女性上位。高校時代、もてなかった男性には降ってわいたような“両手に花”で深刻?な五月危機がおとずれる。恋愛は別にしても、遊び相手に不足はしない。まさにモテナイ教大生にとってはこの教室の男の子だけは破格の待遇である。
教官は文学には文学部長の藤井一五郎教授、前文学部長の入江勇起男教授、受験界の重鎮、成田成寿教授のほか、桜庭信之教授、斎藤美洲教授、福田陸太郎教授、岡本靖正助教授、中尾俊夫助教授、宇賀治正朋助教授、新井明助教授の計10氏がいる。語学には広瀬泰三教授、太田朗教授、梶田優助教授の3氏がいる。その他外人講師が2氏おられる。
女性が多いため近年まで非政治的な雰囲気が強かったが、教授陣が圧倒的に移転反対のため、それにひきずられてか、政治的傾向を強め、今やミンセイ系の指導下に団結を固めている。
米文との交流もひんぱんに行なわれている。卒論は18、19世紀を中心とする作家論が多いが、毎年数人はシェークスピアにアタックする。例年桐葉祭には三年生が英語劇をやるそうで、最近はシェークスピア物がつづいている。
| アメリカ文学 (American Literature) 米文学独自性を研究 |
米文学は39年英語学英文学専攻が改組されて英文から分かれたもの。これは従来の「英語文化」の領域を一括していたものを、米文学の比重が増大しアメリカ文学の独自性が高まっており、独自の方法論が必要になっているところからアメリカ文学の新しい範疇を創出したものである。
一般に外国文学科は単なる言葉の研究にとどまらず、そのことを通じてその社会的背景をも把握する必要がある、という考えに基づいているが、特にアメリカ文学ではアメリカ文化研究を必修にしている。
教官はアメリカ文学史の高村勝治教授と末長国明助教授、神原達夫講師が指導にあたられているほか、英文学教室から入江勇起男教授、福田陸太郎教授、成田成寿教授、中尾俊夫助教授らが出張講義を担当され、評論家の江藤淳氏がアメリカ文化論を講じておられる。
学生は一学年6~7人の少人数で、このことが学生同士のみならず学生と教官の結びつきをつよめている。
アメリカ文学専攻生といえども語学には結構苦労するらしく、一日50~60頁も読ませる先生もいるという。その上卒論は英文タイプ提出するため、その練習をするのも忙しいとか。
| 独語学独文学 (German Language and Literature) 文学に深く 多彩な学生 |
独文学という専攻がどこで政治と接点をもつのかはしかとわからないが、移転推進派にとって最も恐れられているのがこの独文教室である。
教授陣は語学は原田武雄助教授一人であるが、文学はズラリと揃っている。ちなみに元文学部長の星野慎一教授(リルケ)、中村耕平教授(リルケ)、尾住秀雄教授(文芸学)、佐藤静夫教授(トーマス・マン)、石塚敬直助教授(シラー)、井原恵治助教授(ヘルダーリン)、熊田力雄助教授(ゲーテ)と昨年着任された喜多尾道冬助教授(現代小説)がいる。
昨年2月28日の機動隊導入の際、熱心なゲーテ研究者であり正義漢であった桜井正寅教授が発奮のあまり、狭心症を併発して亡くなられた。紛争の渦中におけるあまりにも尊い犠牲を払い、この教室の結束はいよいよ強くなり、西洋史、社会学と並ぶ移転反対の堅城をなしている。そのため、6月に移転推進派が独自にヤマ猫授業を始めた際も、独語独文は全面的に授業を再開せず、文学部教授会をバックアップした。
一方、学生は単なる移転反対にはあきたらないらしく、日本語訳のマルクスをふりまわし、反戦闘争に身を入れ、逮捕されては諸先生方を悩ますものもいる。女性の進出が近年はげしいが、特に最近は他の文学科ノンポリ教室を尻目に異端に走り、左は三派から右は軟派まで幅広く分布し、奇々怪々なムードをかもしている。
先生方は独文研究者養成を願っておられるらしいが、一流企業への受けもよく、ジャーナリズムへ就職していく者が多くなった。
| 仏語学仏文学 (French Language and Literature) 静かなるサロン |
仏文学、仏語学の2講座を擁しているにもかかわらず、募集定員5名と少人数でクラスの密度は高い。
教授陣は現在浪漫主義特にユーゴー研究の辻昶教授、ゾラ、18~19世紀文学の河内清教授およびルソー専門の小池健男助教授、語学の野村二郎助教授、現代文学の花輪光助教授と広い範囲にわたっている。
女子学生も毎年半数をしめるようになっており、クラスにも温和しい空気が漂っている。もっとも温和しい男子学生をしりめに学園・反戦闘争の活動家になった強い女子学生もいる。
一年生は週4回フランス語授業があり、また外人講師による会話も行なわれ、一、二年次はミッチリ鍛えられるという。何はともあれ仏語ができなくては次にすすめない、というわけだろう。教授との個人的な交流も盛んである。喫茶店での講義なんてしゃれたのもあるようで、私大のマスプロ教育などどこ吹く風と、めぐまれた環境である。
卒論はフローベール、スタンダール、ジイド、ランボーなどが多く、18~19世紀のフランスが中心といえる。
| 言語学 (Linguistics) 文学科の異端児 |
文学科といえば、女性が多く、就職には有利、それにカッコイイことこの上ないのだが、この教室だけはそういった華やいだ雰囲気はない。その上一学年5人、計20数名に対し、5人の教官が厳しい目つきで監督しているから、勢い地味でマジメな学生がふえる。そんな学生が耳慣れぬ言語をつぶやいているのだから、一般の人からみれば気狂いかと思われる。しかし、彼らは単にギリシャ語だとかアルタイ語だとかをつぶやいているのではない。人類文明の原点ともいうべき、“言語”の研究を行っているのである。我々が日頃何気なくお世話になっている言語の発生、その文明的意義をここでじっくり考えてみるのもいいだろう。
教授陣はアルタイ語学・比較言語学の河野六郎教授、ギリシャ語学の関根正雄教授、ロマンス比較言語学の田中春美助教授、スラブ語学の千野栄一助教授、そして、移転反対の学生を相手に“検問の鬼”と恐れられた音声学・インド諸語の青柳精三助教授の5氏である。
入学すると英、独、仏のほかにラテン語、ギリシャ語も必修で、少数精鋭主義で徹底的に鍛えてくれる。しかしあまりにもアカデミックな故に、一般企業への就職は思わしくなく、もっぱら教育界へ出てゆくが、研究を掘り下げてみたいむきには修士4名、博士2名の大学院が用意されていて、その点では文学部でももっともめぐまれている。
移転論議の盛んな中で、この教室は、教授諸先生はともかく、学生諸君は団結固く、一部を除いては波風は立たなかったという。
| 社会学 (Sociology) 社会調査を中心にして |
昨年9月、岡田謙教授がお亡くなりになり、空席になっているのが寂しい。諸君が入学してくる頃までには補充されるだろう。
したがって現在の専任教官は、府中市の歴史的研究をしている中野卓教授をはじめ、家族社会学・宗教社会学が専攻の森岡清美助教授、社会調査と社会統計学の安田三郎助教授、労務管理論・経営社会学の間宏助教授の4人である。例年、非常勤講師の特種講義が2つほどあり、かなりバラエティに富んだ講義が展開される。
とはいっても、一年目は北原助手担当のプレゼミと一般教養の社会学概論とによって社会学と対面するにとどまる。社会学とはこんなものとうすボンヤリしたところで、二年目はゼミや専門科目を履修する一方、社会調査の手ほどきをうけて、三年目に社会調査の実習、レポート作成、そして四年目でめでたく卒論というのが順調なコースである。
社会学の研究対象は広範囲にわたり、勉強する気になればなるほど興味が次から次へと湧いてくると思われるのだが、ここ2、3年大学院に進学する者は皆無でおとなしく卒業していった。社会的現象を実証的調査によって究明してゆくという社会学の基本線にのっとって、とにかく社会調査が重視されている。
一昨年から昨年にかけての教育大闘争において、教官側は終始一貫して筑波反対の立場をとりまとまりの良さを示したが、学生内部はまさに四分五裂の状態である。
| 法律政治学 (Legal Political Science) 法律専攻の目的は? |
筑波新大学ができると「飛躍的発展」を達成するという予定なのがこの専攻。文学部内の一専攻として法律政治学があるため、講座が少なく教官が不足し、学外からの講師が多い。それが、一躍法学部という官僚養成所にまで大規模化するのだから「発展」するに違いない。これで「卒業後も文学士では肩身が狭い」という俗物どももさぞや喜ぶことであろう。鶏が裏庭の小屋で飼われていたのが、大規模な養鶏場のケージの中で飼われるようになったこと、そして非情な卵製造器になってしまったことを何となく連想させる「発展」である。
法律とか裁判というのが権力者の私物にすぎないということは学園闘争、東大裁判などで頭脳明晰な諸君にとっては自明だろう。良心的裁判官とか良心的弁護士というのは現代にあっては言語矛盾である。まして「法の目的は正義である」などという幻覚にとらわれている諸君は現実の法の有様を見てみることだ。良心とか正義とかいう甘言ほど人間を抑圧してきたものはないのだ。例年入学早々司法試験受験希望者が「六法全書と無理心中」を図ろうとするようだが、どうみても哀れな心中という気がする。筑波移転反対闘争の中では、戦闘的部分が輩出したが、現在クラスは空中分解中。
現在の教官は、民法の磯野教授・太田助教授、刑法の福田教授、行政法の綿貫教授、憲法の高原教授、日本政治思想史の松本教授、欧州政治思想史の田中教授がいる。
| 経済学 (Economics) マル経と筑波大学 |
経済学といえば、他大学では学部になっている場合が多いが、この教室は学科にもなれない一専攻である。そんなわけで筑波大学創設の際には現在の十倍以上の規模で学部に昇格するとのこと。その際学問から技術へ堕落するとのささやきもきかれる。
他大学の経済学部は多くはビジネスマン養成の面が強く、会計、簿記まで含むが、この教室はそういった「けがれ」の全くない純粋学問、すなわちマルクス経済学である。
教授陣は、そうそうたる顔ぶれで、美濃部都知事も3年前までこの教室におられた。4つの講座があり、経済政策・財政学の長坂聰助教授、欧州経済史の浜林正夫助教授、農業経済学の暉峻衆三助教授、国際経済論の榎本正敏助教授、経済原論・金融論の大島清教授、経済統計学の三瀦信邦教授がおられる。
マルクス主義者で固まっているはずだったが、移転推進の巨頭を生みだして話題をまいた。
学生は概しておとなしいが、処世術にたけた者も多く、在学中は政治運動に首をつっこんでいても、一流企業への就職率は文学部随一を誇っている。英・独の外書講読もあり、がっちり力をつけてくれる。
教育大学のしかも教育学部とは教員養成学部と世の人は考える。でも教員になる率なら他学部の方が高い。「教育学部」の二極再編の中で旧大学の教育学部も再編がせまられている。ここも筑波大学では芸術学科が独立し、高師からの教員養成は「学校教育総合研」の中に解消されるのだという。そんな中で教育学部の意味と未来が問われ直している。
| 教育学 (Educational Studies) 人間としての教育学 |
教育学は雑学だと言われる。教育に関する人文社会科学から、自然科学に至るまで全て教育学の対象となりうるのである。それだけに教育学固有の学問方法がないわけで、それが教育学の今日的悩みである。
しかし、いやしくも教育学は「人間とは何か」「教育の目的は何か」ということが基本的基盤となっていなければならない。つまり、現実の人間の姿を見極め、教育がどのような人間像を追求するのか明らかにしておかないと、教育も生徒を物体の如く扱うことになりはてる。この意味で教育哲学が教育学の基本である。現代は教育目的の混乱の中にあるといわれるが、これを解決するのがこの分野の緊急課題だろう。
この教育目的を受けてそれを実現するのにもっともふさわしい教育内容を選定するのが教育課程学の主なテーマである。
そしてこの内容をいかにして生徒に教えるか、という教育技術学が存在する。これらの3分野が教育学の主たる領域である、というのが教育学の位置づけの定説となっている。
講座は教育哲学(大浦)、日本教育史(唐沢)、外国教育史(長尾)、教育社会学(馬場・石戸谷)、教育行財政(伊藤和)、教育制度(伊藤秀)、学校教育(吉本・真野)、社会教育(平沢・永岡)、教育課程(金子)、教育方法(井坂)、社会科教育(長坂)、人文科教育(倉沢)、理数科教育(和田・吉本)がある。
| 心理学 (Psychology) 人間行動のメカニズム解明 |
脳波研究から社会現象の研究まで、心理学といってもその領域は多岐にわたる。心理学の所属が大学により、あるいは文学部に、あるいは理学部に、あるいは教育学部にと一定しないことにもその性格があらわれているだろう。しかし根本にあるのは常に人間に対する探求であり、一見人間とはほど遠いように見えるネズミやネコの研究も、人間行動のメカニズムを明らかにする上で出発点的なものであり重要な意義をもってくる。そこでE館屋上の小屋には沢山のモルモットなどが実験材料として飼育されている。
心理学を動かすものは、人間に対する旺盛な興味、関心とその理解に対する強い欲求だろう。したがって心理学は自然科学的方法、社会科学的方法を駆使して人間理解に迫ろうとする。近年、統計学の急速な発展の成果をとり入れており、かなり高度の統計的操作が要求されている。電子計算機を利用することも珍しくなくなってきた。また動物生理学の知識も必要とされるので、理科系の素養を欠くことはできない。
心理学科は実験心理学(岩原信九郎助教授・金子隆芳助教授)、比較心理学(丘直通助教授)、性格・社会心理学(長島貞夫教授)、教育心理学(辰野千寿教授)、児童心理学(上武正二教授)、青年心理学(桂広介教授)、講師は藤田統、原野広太郎、高野清純氏がいる。
卒業後の進路は教員は割合少なく1割くらいで心理学をいかした職場が多い。
| 特殊教育学 (Special Pedagogy) 学問としての特殊教育は |
特殊教育学のかかえている問題は極めて大きい。それは、まず第一に「人間存在」探求の一方法論として。また第二に、世に「民主主義・福祉国家」が謳歌されつつも、なお軽視されつづけている特殊児童教育という問題である。
現在おくればせながらも、盲・ろう・精神薄弱・肢体虚弱児を対象とした教員養成学科は全国35大学に設置されている。といっても設置して日の浅い大学が大半であり、本学は付属教育施設、大学院とその内容が充実している点で随一のものである。しかし、特殊教育学の「学問」としての体系は未だ確立されていないのが現状である。本学では教員養成だけでなく、この特殊教育学の研究者養成を大きな使命として大学院研究科がその任にあたっている。43年からは大学院に博士課程が設けられ、学科定員も10名増加され30名になった。このようにようやくこの分野にも社会的な目が向けられつつあったわけだが、筑波審議がすすみ、「新構想大学」の全貌が明らかにされるにおよび、この学科は切りすてられる向きにあるという。
講座は盲教育(佐藤親雄助教授、佐藤泰正助教授)、ろう教育、精薄児教育(西谷三四郎教授、杉田裕助教授)、特殊教育技術(大山信郎教授)、特殊教育生理(寿原健吉教授)がある。
付属施設が多く理療科教員養成施設、リハビリテーション教育研究施設の他に盲学校(上田薫教授校長)、ろう学校(平沢薫教授校長)、大塚養護学校(長島貞夫教授校長)、桐が丘養護学校(加藤勝也教授校長)がある。
| 芸術学 (Study of Art) 奈良京都へ演習旅行 |
本学の芸術学は美術史を中心として、町田甲一教授が奈良朝を中心とした日本美術史を担当し、林良一助教授も東洋美術史を研究している。西洋が欠けているわけだが、これは43年退官し、早稲田に移った沢柳大五郎元教授らの講義で補っている。
クラスは学科の他のクラスと同様一学年6~7人と少人数で、女性も増えつつある。秋の学外演習旅行は主に関西の寺社を訪れるが、日常見ることのできない秘蔵仏等も特に見ることができる。この旅行には4年間のうち2度は参加することになっている。
まだ修士課程だけではあるが、42年から大学院が設置されている。
| 絵画 (Painting) さかんな創作展 |
絵画は明治以来の長い伝統をもちつつ、少数教育であるため、クラス活動や教師との話し合いも盛んで、クラス全体が家族的雰囲気に包まれている。5月桐葉祭をはじめ秋の学年展、他専攻とのグループ展など、活発な創作、展示活動がこのクラスの特徴である。教官は松木重雄教授、吉野純夫助教授で、松木教授は「移転すれば学部昇格」の芸術学科の「夢」を追って移転推進を強硬にすすめている教官の一人。授業は油絵が中心であるが、デッサンや版画プレス室を利用してのエッチングもある。
卒業後は教職に進む者が多いが、民間に進出する学生もある。
| 彫塑 (Engraving) 基礎をもとに創作 |
教育大の彫塑は、オーソドックスな基礎造形を4年間でバッチリ身につけることを根本にしているようだ。このため4年間を通じて基礎をみっちりやる。こういった地道な活動をふまえて外部との接触を求めて、積極的に学外の団体と交流し、あるいはグループ展などのような発表活動を行っている。創作・発表のためにはかなり資金も必要だが、専門を生かしたバイトでけっこうかせげる。
卒業生は2人位が進学、残りは教職につく者が多いが、やがて専門家として成功するものも多いという。43年退官の木村・新海教授に代わり、古川順三教授、小池藤雄助教授が指導にあたっている。
| 書 (Calligraphy) 芸術としての書道論 |
書を学び実践していく基本として古典の学習が重視される。そこで法帳をもとに臨書の勉強をつむ。将来、漢字、かな、前衛等どの方向にすすむにも基礎として古典を踏まえる必要があるからである。書道史、書原理、書技法などの講義があり、上条周一教授の他に専門書家、博物館の研究者の講師が講義している。
書の技術だけでなく書に関する研究をもとめるこの専攻は書を一般の芸術の中にとらえかえし、たとえば西洋美術史からみていこうとしたり、芸術論的・思想的なアプローチが行なわれている。上条教授も、世界の他分野の芸術家と対等に話せる芸術的位置に書をもってゆかなくてはならない、と語っている。
大学院も整備されたが部屋が狭い。が、逆にみれば、院生も一年生も一緒に暮らしているという親近感と連帯感が湧くことになる。
| 構成 (Moulding) 新しい造形の追求 |
グラフィックデザイナーの卵たちの教室である。コマーシャル活動の中でのヴィジュアルデザインはその中心だが、それを総合的に研究しようというもの。造形の基礎としての構成理論・色彩・形態テクスチュア・色光などについての実験研究、写真・印刷などによる新しい造形の可能性を追求している。
学年毎のグループ展もよく開き、各種コンクールに入選するものもかなりある。卒業ののちは、宣伝関係の事務所、会社で働く者が多い傾向にある。
高橋正人教授、三島利正助教授、山名武助教授と本職のデザイナーらが講師として指導にあたっている。
| 工芸・工業デザイン (Craft and Industrial Design) 脚光あびるデザイン学 |
他の専攻が一講座だけなのに比べて、42年度から工芸と工業デザインの2講座を持つようになった。
最近は工業デザイナーとして巣立つ学生が多いが、大学時代にはクラフトからインテリア、インダストリアルデザイン、さらには都市工学、環境デザイン、建築からヴィジュアルデザインの実習となかなか忙しい。
このように「デザイン」といっても、都市構成から室内装飾に至るまでその範疇は広い。 女性もぼつぼつ見うけられるようになっている。
教官は明石一男教授、高山正喜久助教授、五十嵐治也講師が専任。
理学部教授会は移転推進の拠点であるし、移転に伴う大学の変貌が最も象徴的に表現されたのがこの学部かもしれない。それは従来の基礎研究を中心としたアカデミックな学風から一層産業界に要請されている(売れっ子の)応用研究、技術教育の重視への転換である。教授会が移転推進を強行するのとうらはらに、学生内部の移転反対の動きも小さくない。
| 数学 (Mathematics) 諸科学の基礎として |
「数学」を志す諸君でも、他の学科よりいくらか数学ができるといった程度の人が大部分だろう。高等数学にちょっとでも手を伸ばすことは、現在の受験至上の高等教育のなかでは非常に困難であるし、それは現実に大学受験に何の役にもたたない。
実は高校の教科課程のなかでやる数学は、ある意味では相当程度の高いものといえる。ただそれを理解できたと思っていても、経験的に知っているいくつかのパターンから解法に適するものを選び出しているにすぎない。それは断じて数学とは呼べない。
本学の数学教室は、積極的にマスコミにでて行く教授が少ないせいか、あまり目立たないが、充実した教授陣を誇っている。函数論では尾崎繁雄、幾何学では森田紀一、数論では太刀川弘幸、統計学では小西勇雄、確率論では宇田川正友らが担当し、その他、児玉之宏、尾野功教授をはじめ、小泉、塩口、中川、樋口の各助教授、鈴木、難波、国枝の各講師というスタッフである。さらに茂木勇、前原昭二、西村敏男、丸山儀四郎、本尾実らの応用数理学科のバックアップをうけてますます盛んである。
数学科では卒業論文は課せられないが、初年度から専門の講義と演習が必須となる。単位数でいえば、一年で12単位、二年で18単位と、なかなかきびしい。
卒業生は教職に就く場合が多いが、最近は企業関係も伸び、10人近くが何らかのかたちで進学する。
都内数学科学生でつくる研究サークル都数研の中心でもある。
クラス活動も雑誌編集、合宿と盛んで、最近は女子の進出もめざましい。
| 応用数理学 (Applied Mathematics) 技術者でなく研究者養成を |
応用数理学科は、応用代数学(遠藤静男助教授)、数理論理学(前原昭二教授)、推理解析(広瀬健教授)、計算機構(西村敏男教授)、確率論(丸山儀四郎教授)、情報理論(本尾実教授)、応用解析(茂木勇教授)の7講座がある。これから判断し、応用面が重視された数学科と思われる人もあるだろうが、決してそうではなく、現代数学そのものがここにあり、学生は一年次から数学の基礎をしこまれる。
推理解析の広瀬教官が研究されているのは基礎論で、茂木教授は幾何学の大家であり、情報理論というゼミはない。だから応数というより、第二数学科と呼んだ方が的確だろう(名称などどうでもよいことだが)。
教室の特色は、教官の平均年齢が非常に若いということである。「若いことはよいことだ。」数学科と比較しては失礼だが、筑波闘争の中でさほど進歩的とは思えない教官も、数学科があまりに反動的なため、他教室の学生は「応数には良い先生ばかりいる」といったものだ。とにかく、授業再開後、教官と学生の断層は他の教室よりは少なかったようだ。 ただ、赤、服部両教授が去られ欠員となったままで、その分また若くなったが、惜しまれる。
これからも優秀な教官が筑波へのゴタゴタを嫌い、去られることが予想される。新大学が待っているから、数学を単に技術的に考えて入学される人には障りがないが、充分留意されたし。
ゼミの人気は、計算機構、基礎論から確立論に移りつつあるようだ。就職状況は、今年は一人も大学院に行かないが、例年は8人位。企業には3分の1程でバラエティに富んでいる。数学は教職は労せずとれるが、教師になる人は多くはない。最後に、学生には民青もいるから、非常に面白いクラスだと思う。
| 物理学 (Physics) 優秀な教官 明るい雰囲気 |
教育大で一番有名な専攻がこの物理学である。学長が続々と物理学教授から出ている。ノーベル賞の朝永振一郎は60年安保のときの学長だった。そして教育大闘争の発火点ともなった学長選挙で選ばれた三輪光雄、彼は学長室はおろかキャンパス内に一歩も足を踏み込まないで――学生と全く接触しないで――「紛争」の責任をとって辞めた。その後釜に、同じく責任をとって評議員から学長代行に昇格した宮島龍興。彼はこの一年間罪悪の限りを尽くしてこのたび学長にまた昇格する予定だ。そしてこの宮島を陰であやつる黒幕が福田信之。実力No.1、ミスター教育大。ニックネームはヘルツといい、ドイツでもドクター・ヘルツで通るというから相当馬鹿にされているのではないかと思われる。オストラシズムが教育大でも行なわれれば、絶対確実に追放される人物の筆頭だ。
教授はこの宮島龍興、福田信之らの他に、一流の右翼文化人になったと噂される小西文学部教授と共に筑波大学創設のための海外視察に行くことになっている三雲昂、宮本米二らがいる。
| 応用物理学 (Applied Physics) 「理論」の強力なバックアップとして |
物理学科の設備不足の面を補い、世界的水準に達する「理論」面に強力なバックアップをするために長期的展望の下に、積極的に問題を解決する方向で42年に新設されたもので、当初はほとんど設備を持たぬまま設立された。
しかし現実に理学部の将来計画と物理学科の水準を考慮したとき、本学科の設立と充実は必然であったといえる。
初年度の講義は物理学科の学生とほとんど同じで、選択は学生の自由に任された。教授陣は、物性論の戸田盛和、核磁気共鳴の小島昌治、原子核実験の真田順平、沢田克郎、助教授には萩原茂男、高野文彦、栗山克美、原康夫、楢原良正、松浦悦之、阿部聖仁、石塚浩と多い。実験を中心に講義をすすめていく方針である。
応用数理につづいて、応用物理を設けた理学部の応用面に対する力の注ぎ方がうかがわれるが、なにせ設備に莫大な費用と敷地が要求される応用部門だけに困難も多いが、応用部門の充実がそのまま理論面に与える影響が無視できないものであるだけに、その成功の可否が今後大いに注目される。すべては「筑波」次第ということかもしれぬ。
| 化学 (Chemistry) 実験とクラスづくりに |
校庭で白衣を着て、ソフトボールやバレーボールをしている学生がいたら、ほとんど化学科の学生、これは化学の学生と思ってもいい。学生の怠慢を表すものではない。どういう訳かといえば、長時間かかる有機実験等の結果待ちか、学年対抗のソフトボール試合をしているのである。
クラスづくりはしっかりしている。これはチームワークを要求される化学実験に起因するのだろうか。
教授・研究室の陣容を紹介すれば、無機分析化学-稀土類元素の分析化学的研究等が長島弘三、無機化学-地球上及び内部等を構成する物質の化学成分・化学組織・同位体(アイソトープ)を知ることによってそれらの物質の物理的化学的相互関係における生成過程の研究が三宅泰雄、有機化学-化学発光及び生物発光に関する研究等が杉山登、生化学-有機天然物の構造研究及び生物発光の問題が柿沢寛、物理化学-物質の電子状態の研究等が鐸木啓三、高分子化学-高分子物質の溶液物性に関する研究が小寺明、そして放射化学-原子核反応直後の元素の特異性に関する研究が池田長生の各教授、といったところである。助教授は富田功、松尾禎士、表美守、木村幹の各氏である。
卒業生は教職に就く者は少なく、大学院進学、官界・業界へ進む者が半分以上を占め、就職率は100%である。
| 動物学 (Zoology) 境界領域に人気 |
動物学は、発生学・生理学・形態学・生態学の4講座からなる、地味でアカデミックな雰囲気をもつ学科である。発生学では動物の形態が対象となる。本学動物学の伝統を形成するうえで貢献の大きかった丘英通(本学名誉教授)の発生学を継承して、現在、林雄次郎教授と渡辺浩・関口晃一両助教授が研究に携わっている。発生学はさらに、実験発生学と細胞分化の問題にわけられるが、内容においては、いずれも生化学的である。関口助教授はカブトガニを用いた研究やウニのフ化酵素の研究をしている。生理学は動物の器官の働きを研究する分野である。松井喜三教授は電気生理学を中心に研究している。最近どの学問でも境界領域が脚光を浴びているが、動物学でもその現象はあらわれており、生化学が人気をあつめている。発生学にはもう一人碓井益雄教授がユニークな研究に従事している。
各学年とも週2回実験があり、二、三年になると夏休みに下田の臨海研究所での実習がある。教授と起居を共にしてのこの実習は、マスプロ教育が嘆かれる今日かなり恵まれた存在といえよう。卒業後の進路としては教員は多くなく、大学院進学、研究所など研究生活に入るものが多い。
ここ数年来、動物学と植物学の教授達の間で、二つの分野を一緒にして、生物学という新しい教室をつくろうという構想が語られてきたが、現在は「筑波」の前に影をひそめてしまったようだ。
| 植物学 (Botany) 生命の神秘への挑戦 |
植物、これから何を想像するであろうか? 花・葉・茎・・・。
本学の植物学科は、文理大以来の伝統をもっており、東大等が応用面において数々の成果をあげているのに対比してみると、基礎理論の徹底的な研究に従事しているといえるだろう。講座は4講座あり、「分類・生態学」の伊藤洋教授、「細胞・遺伝学」の林孝三教授のシダ研究、「生理・生化学」の西沢一俊教授の炭水化物研究、印東弘玄教授のカビ類の研究(一般植物・微生物学)など、いずれも基礎的な地味な研究だが、その研究内容をみると、日本の第一線の水準をいくものである。授業においては、分類学に特色があり、その一(シダ以上の高等植物)その二(シダ以下の下等植物)というように細かく分けられている。
植物学あるいは生物学は、他の自然科学とは多少異なる趣きをもち、物理学・化学等の個別の法則性を総合化することによって、はじめて生命の神秘を解明することができるという複雑性をもっている。だから学生は、専攻の植物学だけではなく、物理・化学等の授業も真面目にうけなければならないので、教育大生の模範生的な学生が多くなるのもうなずかれよう。昼休みでも白衣の実験服を着て占春園で生命の探究をしている学生をみれば植物の学生と思ってまちがいはない。
| 地理学 (Geography) 特殊科学から総合科学へ |
本学の地理学教室は、自然地理学=町田貞教授と井口正男助教授、人文地理学=尾留川正平教授と山本正三助教授、地誌学自然地理学=関口武助教授、地誌学人文地理学=浅香幸雄教授、水収支論=山本荘毅教授と市川正巳助教授、の5講座で構成されており、その規模においいても研究・教育の内容においても日本一であることは論をまたない。
自然地理学講座は地形学、人文地理学講座は経済地理・人口論・農林水産業、地誌学自然地理学講座は気候学、地誌学人文地理学講座は歴史地理・人口・都市地理・交通地理、水収支論講座は陸水学等々の研究・教育をしている。これらの成果は学会の機関誌等に記載されており、また当教室では毎年東京教育大学地理学研究報告なるものを出しており、これは他大学には類を見ないすぐれたものである。本年は第14巻を編集中である。勉学面において特筆すべきことは、卒業までに最低4回、教授、助教授、助手とともに野外(フィールド)に調査におもむく野外実験(巡検)があることであろう。教官、学生が共に調査研究するものであり、地理学の本質にせまるのもこの時であり、がっちりしぼられるし、また学問論の花が開く時でもある。
学生数は学部一学年30名程度、大学院、修士、博士34、5名である。
学部学生の進路は、教育界2分の1~3分の1、大学院3分の1、その他は民間に就職している。
| 地質学鉱物学 (Geology and Mineralogy) 「民主的」な教室運営 |
地質鉱物学専攻は理学部北側の1階と地階に研究室をならべ廊下の両側におかれた岩石標本、化石類が一目でそれと感じさせる。
教授陣は8名で、岩石学・構造地質学の牛来正夫、古生物学・地誌学の大森昌衛、地質調査法の藤田至則、鉱物学・層位学の渡部景隆、解析鉱物学・反応学の須藤俊男、鉱床学の宮沢俊彌、地史学の橋本亙がいる。
移転推進勢力の強い理学部でも、この専攻は比較的批判的態度をとる教官が多く、学生との結びつきも理学部では最も良い。筑波闘争の中で、同教室の雨宮委員長が処分された時にはクラスに対策委をおき、積極的に法廷での処分撤回闘争を闘い今日に至っている。
アポロ11号の成果はいち早くこの教室に伝えられ、旧来の地球物理学、鉱物学に修正が加えられている。そして今までの地味な岩石採集から一躍脚光をあびつつある学問へ脱皮している。
前身は農業教育専門学校であったが、全国で数少ない林学科を擁しており、総合的な農学部になっている。とくに農業の性格上、物理、化学、工学との関係、あるいは社会科学との関係が密接である。農学部は大塚から離れているため、一般教育など不便だが、学部祭など家族的雰囲気が濃厚である。
| 農学科 (Agricultural Science) 化学、物理学の知識も |
農学科は農学専攻と応用生物学専攻とに分かれており、一年後各専攻に分かれる。農学科全体として農業生産に関する自然分野が網羅されている。
農学専攻は農作物、園芸生物、家畜を対象として、その生理、生態、遺伝などの特性、生産物の品質、利用そして営農などについて基礎的ならびに応用的研究を行う。講座は5講座で作物学(西川五郎教授)、総合農学(菱沼達也)、畜産学(斎藤昌蔵教授)、園芸学(山崎肯哉教授)、育種学(細田友雄教授)がある。
応用生物学専攻は植物や植物生産物に損害を与える動植物に関する生物学的研究、防除技術の基礎や応用について研究する。講座は3講座で植物病理学(徳永芳雄教授)、応用動物学(藤井和重教授)がある。
助教授陣には、花田毅一、千葉弘見、岡田正順、室賀政邦の各氏がいる。
学生の要求される知識はもちろん生物学が中心だが、これからの発展を考えてみると、化学、物理学的な知識も当然求められてくる。また、社会・経済知識も重要である。
卒業後の進路は教職がかなり多いが、農林省の各研究機関、地方自治体の農業試験場などに多く進んでいる。また近年は民間会社にも入っている。
| 農業化学科 (Agricultural Chemistry) 生産物加工利用の基礎理論 |
農業化学科は農作物の生育、増殖及び農業生産物の加工利用に関する基礎理論・応用を研究している。
専攻は6つに分かれ、農薬化学では昆虫誘因剤に関する研究を主に行っているが、これは新しい昆虫防除剤の開発をめざしている。生産化学は、植物界に広く分布するポリフェオール性物質についての研究を行っている。食品製造化学では食品成分中特に重要な蛋白質と脂肪を中心に研究し新しい食品開発をめざしている。植物生理化学では酵素の研究が進められている。肥料及び植物栄養学では植物体内におけるカルシュウムの作用についての研究が行われている。また土壌学では、火山灰土壌の生成論的研究が進められている。 クラスは各学年30名で、学内活動にも進んで参加する学生が多い。
卒業後の進路は、食品工業が主で、医薬品、工業化学関係一般、教員とつづいている。 教授陣は、生物化学講座が滝野教授、今川助教授、食品製造化学講座は小原教授、小笠原助教授、植物生理化学が藤岡教授、新井講師、農薬化学が武藤教授、須賀原教授、肥料及び植物栄養学講座が出口教授、太田助教授、土壌学は弘法教授、大羽助教授である。
| 農業工学科 (Agricultural Engineering) 土地改良事業の一環を研究 |
農業工学科はさらに農業土木と農業機械に分かれる。
農業土木は農地工学、排水工学、灌漑工学の3講座から成っている。農地工学は、土壌物理学を中心にして農地整備、土質土地保全、客土、干拓等の土地改良事業の一環を研究している。排水工学では、水田地域および土地の流水機構、灌漑水収支、還元水に関する研究など実証的研究が多い。灌漑工学は、水源施設の計画、耕地への送配水の研究ならびに水利構造物の設計に関する研究を行っている。
農業機械は、農業機械学と農業施設学の2講座に分かれ、農業機械は、農業の近代化のために労働生産性を高める立場からの農業機械の開発と普及のための基礎的研究を行っている。農業施設は新しい分野の学問であるので、研究内容もはっきりしていないがサイロの研究等がなされている。
学生は個性的でのびのびと研究している。就職も土木、機械関係が多いが、注目されるのは国家公務員試験において全国第一位を占めていることであろう。教授陣は農地工学が岸上定男、灌漑工学が内藤利貞、排水工学が野口正三、農業機械学が山中勇、農業施設学が森野一高の各教授、その他、山沢新吾教授、穴瀬、山本、中川、吉崎の各助教授がいる。
| 林学科 (Forestry) 演習林での生活 |
林学科は、森林について、政治・経済・地理・地質・動物・植物・工学などのあらゆる面から研究していく、農学部には数少ない「総合科学」の一つである。だから山の中にこもって森林を調査するようなことのみを「林学」というイメージから受けるが、先の様に多方面からアプローチする科学であり、一度山に入るとあらゆる教室で学んだ知識が応用できる。森林にいる動植物、山の気象、治水、林学を中心とする会計、そして木材のことなど・・・。また林業政策と、それを通じて歴史、地理という具合である。
長野県野辺山、静岡県井川などの付属演習林で卒業まで7、8回の実習があり、1週間泊まり込みで教授陣からシゴかれる。
講座は4つで、造林学では、陣内教授を中心に森林を作り育てる研究、利水防砂学では、藤井真一教授を中心に治山治水・森林利用の研究、森林経理学では、篠崎哲教授を中心に林業経営に必要な技術の研究、林政学では、山本光教授を中心に林業の歴史、地理、林業政策等の研究が進められている。
この科の学生は、山奥での林学実習にたえるだけの体力とねばりが要求されるので、そのせいか一般に物事に動じない大陸的性格の持ち主が多い。女性は原則として敬遠されるそうだ。夏休みには、実習の成果を生かして営林署などでアルバイトをする学生も多い。クラス活動も盛んで、週に一度自主ゼミナールが開かれている。
就職先は、営林(国有林関係が主)、一般会社、県庁などが多いが、教員になるものもいる。
| 木材工学科 (Wood Engineering) 合板・積層材の製造理論 |
この学科では伐採した木材の加工、利用の研究を行っている。
講座は木材加工と林産化学の2つに分かれている。
木材加工では、木材の組織構造、木材の理学的性質、木材の強度などの木材の基礎的性質の研究を根幹とし、木材の加工方法、合板、積層材などの製造理論及び方法の研究を行っている。
現在研究室としての大きなテーマは木材の切削加工関係で、卒論もこのテーマ関係が多い。
林産化学は、樹木及び林産物の化学的研究と林産物の合理的利用の研究を行っている。現在進められている研究には、放射線照射による木材とプラスチックのクラフト重合、木材の物理的化学的性質の差異とパルプ強度の関係、台湾産木材のパルプ化の条件とパルプの物性等がある。
四年次には木材工業関係の各種工場の見学旅行があり、就職もパルプ、合板、木工関係が多い。
教授陣は、木材加工が林大九郎教授、林産化学は岸本定吉教授、田島俊雄助教授である。
| 農村経済学科 (Rural Economics) 農村社会の全面的研究 |
農村経済学科は、その名から連想されがちな、農村を中心とする経済学、経営学のみの研究だけではなく、広く農業社会としてとらえ、農業をめぐる経済環境、農村社会、農民教育などの研究が行われている。農学的色彩よりも文学部の社会学的色彩が強い分野である。
講座は4つあり、この科の基礎となるべき農政学は、三沢嶽郎教授を中心に農業政策、農地価格、貿易等についての研究がなされ、農業計算及び経営学は、加用信文教授を中心に、農業経営、市場、簿記等の研究を行っているが、この科の特色は、林純一教授を中心とする農業社会学と加藤惟孝教授を中心とする農業教育学にある。ここでは農民生活の実態調査、農業改良普及事業や共同化の指導等を行ないながら、常に農村との接点をもちつつ、現代農村の諸問題、例えばますます深刻化する青年層の都会への流出、出稼ぎ、“三ちゃん農業”等についてもアプローチしている。
その他、市古浩、江島一浩、竜野四郎、浜田陽太郎の各助教授がいる。三沢教授は米価審議会に学識経験者として参加、農政転換期の荒波にもまれているようだ。
学生は闘争に参加するものもあれば、勉強するもの、どこかで何かを、と多彩である。就職先は、農業団体、民間会社、県庁で約7割余を占めているが、公務員、教員になるものも少しはいる。
| 生物化学工学科 (Biochemical Engineering) 農学と化学工業のかけ橋 |
生物化学工学という学問の歴史はまだ新しく、約20年と言われる。科学の高度な発展は必然的に専門の細分化と基礎科学の融合を不可欠とする。この学問もそういた必要性から誕生し、近年その学問的意義が広く認められつつあり、現代科学の花形的存在になりつつある。教育大に同名の学科が発足したのは6年前で、国内唯一の科である。
本学科の主眼は、発酵ないし応用微生物産業を化学工学の一分野として把握することにある。したがって農学部の一学科という印象はきわめて薄く、むしろ工学部的な印象が強い。他の学科に比して基礎科目や関連専門科目等の必須履修科目が多く、教職を取ることは極めて困難である。
講座は4講座で、工業微生物学教室(阿部又三教授、田渕武士助教授)、化工単位操作教室(小林次郎教授、吉留浩助教授)、培養工学教室(上田清基教授、高橋穣二助教授)、反応工学教室(宮崎安太郎教授、戸田清助助教授)である。また学部付属の木材糖化研究所(所長・小林達吉教授)も本学科と密接な関係がある。
本学科の卒業生の進路は明るく、今年の卒業生の場合は、大学院進学8名、他就職希望者全員就職でしかもすべて春に決まってしまう売れ行きである。就職は、医薬、高分子化学、工業プラント設計、微生物関係方面が多いようである。
体育学部の研究水準はそのまま日本の水準である。学部があるのは国立で唯一、私立でも二つしかない。最近は選手養成、教員養成だけでなく研究にピッチをあげている。なにぶん体育は生まれてから日の浅い学問であるため、武道科のように政治的利用に乗ぜられることもあるが、科学的な体系へと突き進んでいる。
| 体育学科 (Sports Studies) 体育とは文化 |
体育学とは、身体的な活動を中心にすえて、その中で身体的・精神的な面から人間の発達をみていこうとする学問であるといえる。芸術学が芸術という文化を対象とするのと同じ意味で体育文化の研究ともいえよう。
体育学科は、体育学、体育史、体育社会学、体育心理学、体育管理学、陸上競技、球技、舞踊、野外活動、体操の10講座に分かれて自然科学・社会科学的な見地からも研究にとりくんでいる。
体育学では現代の体育のあるべき原理とその方向を示し、その原理の学問的体系の確立をめざしている。体育史では体育をいろいろな角度から歴史的に研究する。古典的体育書の解説や批判、近代スポーツの成立についてなどである。体育社会学では体育、スポーツ、レクリエーションなどの問題を社会学的な角度からとらえて研究する。体育心理学では単なる教育心理学ではなく体育そのものにおける心理学的な問題の解明を行なっている。体育管理学では体育の場の条件を整備するという体育管理の課題に向かって、体育の管理原則や管理手順を体系化しようとしている。陸上競技ではスポーツのトレーニング法や基礎体力の養成の問題を取り扱っている。球技ではボールゲームの技術や学習場面における感覚知覚的な機能について研究している。舞踊では舞踊の心理や社会的特質など、野外活動では自然研究、集団生活などの教育内容を含んだ野外活動を体育的見地からみている。
| 武道学科 (Budoology) 武道の近代的体系を |
昨年、体育学科から分かれ、剣道、柔道、武道論、弓道の講座をもっている。
武道はとかく政治的にとりあつかわれることが多々ある。戦前の精神修養の名の下にあった軍国主義への利用、逆に侵略性を形づくったものとして戦後占領による禁止処置など。このような社会的動きのなかで、「文化財としての武道の学問的研究と共に、優秀な武道教育者を育成し社会に応える」目的で設置された。つまり武道はそのような政治的状況のため、また古典的在来競技のため科学的研究が十分なされていない。例えば柔道は世界的スポーツとしてオリンピックにまで登場したにもかかわらず、体系的研究がなされていない。大学という研究の場で合理化近代化をしなければならないというわけである。
比較学的、史学的、医学的アプローチなど未知の体系を開拓する新しい部門として発展させようとそのスタッフが昨年度中に整えられた。剣道は大滝忠夫教授、柔道の中野八十二教授、武道論の渡部一郎助教授、その他松本芳三教授、坪井三郎助教授、竹内善徳講師と設置以来年々拡充された。渡部助教授の前任は日本史教室で、史学的アプローチをしようというわけだ。
しかし、本学科設置課程をみると、体育学科が基礎学的な体育学科、方法学的な体育運動学科(外来種目)、武道学科(在来種目)の3学科に再編成の予定を外来種目は体育学科に入ったまま。方法学的な一部が武道科として認められた。つまり、設置過程は非常に政治的なにおいがする。
| 健康教育学科 (Health Education) 内部的変化を追求 |
耳慣れない学問であるが、健康教育学とは、健康について精神的・身体的・社会的に幅広く研究していく学問である。戦後体育専門学校と高師の合併により生まれて新しいが、内容的には歴史があり、まだまだ未開の分野も多く将来性をもっている。体育学科が体育スポーツを通して対社会的にかかわるのに対して、健康教育学科では内部的変化をより微細に深く追究しその予防医学的、体力増進という面に特殊性を示す。医学博士の教授の多いのもそのためである。
現在、解剖学、生医学、スポーツ医学、衛生学、健康管理学の5講座がある。身体内部の諸機能の変化を研究する解剖学、筋肉・骨格などについて究める生医学、医学的な面から身体を追究するスポーツ医学、個人環境衛生について広く研究する衛生学、学校工場の衛生管理、健康教育についての健康管理学。
三年から専門教育にはいり、教室の雰囲気はグッと学問的になる。スポーツサークルに入り厳しい訓練を続ける学生もおり、文化サークル研究会で充実した生活を送る者も多い。夏の水泳実習、冬のスキー実習には全員参加するはずという。