 (注)朝永振一郎氏(1906-1979)は京都大学の出身であるが、理化学研究所仁科研究室を経てライプチッヒ大学に留学(ハイゼンベルクに師事)、帰国後1941年に東京文理科大学の教授となられ、新制東京教育大学の発足に伴い1949年から1969年まで、東京教育大学理学部物理学科および光学研究所の教授を務められた。その間、1956年から1962年の2期6年間(1期4年間、再任2年間)にわたり、東京教育大学の学長を務められ、東京教育大学の発展のために尽力された。朝永氏が学長をされていた時代は後年教育大関係者によって「朝永時代」と呼ばれるようになり、東京教育大学がもっとも輝いていた時代、東京教育大学の黄金時代と見なされるようになった。教育大学新聞会は、学長退任直後の1962年、朝永教授に過去の「思い出ばなし」の連載企画を提案したが、教授はこれを快く引き受けられ、24回にわたって当「教育大学新聞」の紙面を飾っていただいた。当然、当会刊行の「文理科大学新聞・教育大学新聞 縮刷版」に掲載されているわけであるが、「縮刷版」をお持ちでない方にも、これを公開するのは公共の利益であると考えられるので、ここにその内容を紹介することとしたい。
(注)朝永振一郎氏(1906-1979)は京都大学の出身であるが、理化学研究所仁科研究室を経てライプチッヒ大学に留学(ハイゼンベルクに師事)、帰国後1941年に東京文理科大学の教授となられ、新制東京教育大学の発足に伴い1949年から1969年まで、東京教育大学理学部物理学科および光学研究所の教授を務められた。その間、1956年から1962年の2期6年間(1期4年間、再任2年間)にわたり、東京教育大学の学長を務められ、東京教育大学の発展のために尽力された。朝永氏が学長をされていた時代は後年教育大関係者によって「朝永時代」と呼ばれるようになり、東京教育大学がもっとも輝いていた時代、東京教育大学の黄金時代と見なされるようになった。教育大学新聞会は、学長退任直後の1962年、朝永教授に過去の「思い出ばなし」の連載企画を提案したが、教授はこれを快く引き受けられ、24回にわたって当「教育大学新聞」の紙面を飾っていただいた。当然、当会刊行の「文理科大学新聞・教育大学新聞 縮刷版」に掲載されているわけであるが、「縮刷版」をお持ちでない方にも、これを公開するのは公共の利益であると考えられるので、ここにその内容を紹介することとしたい。
なお、この「思い出ばなし」を連載中の1963年、朝永教授は日本学術会議の会長に就任されて多忙となったため、本来の「思い出ばなし」は第12回までとなり、内容的には継続しているが、第13回以降は「滞独日記」という形式になっている。「滞独日記」はおよそ丸1年分となっているが、「もう提供する材料がなくなったのでこれでおしまいにしたい」とのことで、第24回をもって終了となった。ヒトラー政権下、第二次大戦直前の留学体験についてのご本人の貴重な日記である。このような貴重な記録を「教育大学新聞」に提供して頂いた朝永教授にはあらためて感謝の意を表したい。
また、当連載終了後の1965年、朝永教授は湯川秀樹氏につぐ日本人として2人目のノーベル物理学賞を受賞された。その際の当新聞会のインタビューにも研究費の不足を嘆き、「ストでもやりますか」と冗談を飛ばすような気さくな人柄であった。定年退官は移転問題での紛争中であったが、当時は光学研究所長の職にあって移転問題で表面に出ることはなかった。(光学研究所は筑波移転に賛成の立場だったが、問題の平和的解決を希望していた。)弟子たちの暴走をどう見ていたかは不明であるが、朝永氏本人は「筑波大学」とは無関係であり、かつ朝永学長は大学の民主的運営を心がけ学生からも絶大な信頼を集めていたが、筑波大学はその正反対の志向性をもつ大学であるから、不肖の弟子たちが朝永氏の遺業を顕彰すると称し、筑波大学内に「朝永記念室」なるものを設置しているのはいささか不遜というものであろう。朝永氏は退官後、「世界平和アピール七人委員会」のメンバーとして亡くなるまで世界平和の実現のために尽力されていた。
★
なお、「教育大学新聞」(縮刷版)からの転載にあたり、基本的には原文通りとしましたが、一部の明白な誤植は訂正しました。また、新聞紙面上では、行末ではみ出す句読点は本来なら一字送って次行に入れるべきところですが、文字送りをせずに省略している場合が多く、これらは適宜句読点の追加を行いました。また、本文内容との整合性を考慮し、第9回と第10回でカットとして使用されている写真の入れ換えを行いました。
本編
 第1回
第1回 第375(1962/9/10)号
学長をやめて、このごろはいくらかひまである。しかし、どうせまたいろいろ用事を持ち込まれるにちがいないから、そうなる前に昔の思い出などを綴っておこう。
古めかしい煉瓦建築の入口を入ると、灰色に汚れたしっくい壁の暗い廊下に、ほこりくさい空気がよどんでいる。この陰気で沈滞したようなふんいきが京都大学の物理科に入ったときの第一印象であった。
今から思い出してみても、学生時代に楽しかったこと、生きがいを感じたことなど、一つもなかった。一つには健康がすぐれなかったせいもあって、何かわけのわからぬ微熱が続いたり、不眠になやまされたり、冬は必らず二度も三度も風邪をひき、胃弱、ノイローゼ、神経痛、そんなぱっとしない状態がいつまでもつづいた。一方講義はちんぷ平凡に思われ、物理学というものに何となくあこがれのようなものを感じていただけに、それは大変な幻滅であった。
中学五年生のとき、有名なアインシュタインが来日した。何もわからぬのにジャーナリズムはいろいろと書きたて、なまいきな中学生もそれに刺激されて、なんにもわからぬのに石原純先生の本などを手にしたりした。時間空間の相対性、四次元の世界、非ユークリッド幾何の世界、そんな神秘的なことが、このなまいきな中学生を魅了した。物理学というものは何と不思議な世界を持っていることよ、こういう世界のことを研究する学問はどんなにすばらしいものであろうかと思われた。
新しい量子力学が発見されたのは一九二三-一九二五年ごろのことであったから、それはちょうど高等学校の学生時代のことであった。化学の講義で、原子構造の話などもでてきたが、講義では、ボーアの理論がさも新しいもののように話された。これはとても革命的な新理論で自分にもよく理解できない、などと化学の先生は話をした。けれど考えてみれば、それはそのときすでに十年前に出ていた古い理論であった。
高等学校三年生になると、そろそろ自分の専門をきめねばならぬことになる。生物系へ進むものは動物解剖の実習などをやり、数物系へ進むものは力学をやる。どちらをやるか、いくらか迷ったが、ついに力学の方をやることにしたのは、中学時代のアインシュタインからの当然の帰結でもあったのだろうか。
その力学の先生は、そのときちょうど京都大学の物理科を出たての新進の分光学者であった。先生は実験家であったが、分光学という専門は量子力学と関係が深いので、この先生の口を通していろいろなことを聞くことができた。電子が波であるという考えがあるということ、また、マトリックス力学という、とてつもない新しい理論があるということ、それから、日本の大学でやっている物理などは、もはや古くさくてだめなのだといったようなことがこの若い先生のことばからうかがわれた。

こんな背景をもって入ってみた大学では、実験室はうすぎたなくほこりにまみれた古めかしい機械で、ほそぼそとやっているらしい二番せんじの実験、他方、理論の講義は無味乾燥な数式の氾濫、それを一つ一つノートにうつしとっていく退屈な作業。あんな神秘的に思われた相対論も、ここでは物理的な肉づけも、哲学的な深遠な考察も全くもたない、ただの数式のいぢくりまわしにすぎない。電子が波動性を持っているとか、マトリックス力学というような、若い、なまいきな学生の好奇心を極度にかきたてるような話は一かけらも出てこない。
しかし、この退屈な教室の中にも、沈滞した空気のなかにときどきふき込んで人人を生きかえらせる冷風のように、新鮮な空気のただよう時間もあった。それは岡潔先生と秋月康夫先生の数学演習の時間であった。
附記
新聞会の注文で思い出話を書くことになったが、はじめの三回ほどは雑誌「自然」九月号に出したものと重複する。
(写真は京大正門/題字・サインとも筆者自身によるもの。)
第2回 第376(1962/9/25)号
数学演習というのは、毎週十題ぐらいの宿題が出て、次の週に黒板の所で解いてみせるものだが、大いそぎで黒板に出て、やさしい問題に手をつけてしまわないと、乗物にのってまごまごしている間に席をとられてしまうように、あとは手ごわい問題ばかりが残ってしまうものである。しかしすばやく席をとろうなどとすると、胸はどきどきするし、それは何とも浅ましいことのように思われた。そこでいっそのこと、一番むつかしい問題を一つか二つだけやっておくという手を使うことにした。そうしておけば、そんな問題にあまり手をつける者はないので、そうあわてないですむことになる。やってみると、いくらむつかしくても、一題か二題だけに集中して一週間の時間をかければ、何とか解けることがわかった。何日も何日も考えつづけて、むつかしい問題が解けたときのよろこびは、たとい答のすでに出ている練習問題であっても、それは純粋に学問的な創造のよろこびに近い。
岡先生にしても秋月先生にしても、今ではレッキとした大数学者だが、当時はまだ大学を出たての若僧で、われわれにとっては、兄貴のように親しみやすかった。それに、すでに智的好奇心も探究意慾もかれてしまったような老先生の中で、この二人はいかにも若々しく、情熱を研究にささげているらしい空気が学生に伝わってくるように思われた。若い先生というものは、学生にわからせるというよりも、自身の興味に溺れて、話が脱線することもよくあるものだが、そういうとき、わからぬままにかえって好奇心をそそられ数学の新しい動向の片鱗がみえたような気がして、今まで習った古くさいものとくらべて、それは何とも魅力あるもののように感じられるのであった。

大学三年生になって専門をきめるとき、身のほども知らず、量子力学の勉強をやろうと思ったのは、新しものずきという、若気のいたりからであった。実験物理を選ばなかったのは、一つは健康上の理由で、学生実験のとき、一、二時間立っていても痔のぐあいが悪くなるありさまでは、とてもだめだと思った。
その時分、新量子力学を理解していた先生は教室には誰もいなくて、ただ二、三の野心的な先輩が独学でそれをやっていたので、それらモダンボーイたちの仲間に入れてもらい、いろいろ指示を受けた。このとき同じ方向に進もうとした同級生に湯川秀樹くんがいたことは、大きな力ともなり刺激ともなった。時には刺激が強すぎていささか閉口したこともあったが・・・。
身のほど知らずのむくいは、たちまちやってきた。大学入学以来病気ばかりしていたので、たくさんの試験が受けないままに残っていた。一年生のとき受けるべきものを二年に残し、二年生のとき受けるべきものを三年に残し、三年生になると、もはや次の年に残すわけにいかないので、試験が山のように積み重なって、巨額な借金を前にした債務者の心境もかくやとばかり思われた。その上に量子力学の論文を読んで卒論をでっちあげねばならない。何しろ、量子力学はまだ出来たての学問であったので、それに関する教科書などない。原論文だけが唯一の資料である。ところが論文というものは教育用には書かれていないので、その理解に必要な予備知識を持つためには、その論文に引用してあるおびただしい論文を一つ一つ読んでいかねばならない。そのおびただしい論文を理解するためには、更にまたそこに引用してあるたくさんのものを読まねばならぬ。論文の数は、末広がりに、殆んど無限にまでひろがっていく。これは大変な仕事であることが、あとになってわかった。しかし今さらやめるわけにもいかず、全く息を切らしながらとにかくまがりなりにも卒論をまとめ、試験もどうやらおなさけでパスしたけれども、そこに見出したものは、全く疲労困憊してしまった自分自身であった。くたくたになったあげくに、何もわかっていないのだ、という劣等感のかたまりのようになって、おどおどしている自分自身であった。
(写真は京都大学の卒業記念写真。円内は朝永氏。集合写真には朝永氏の他、湯川氏も含まれている。)
第3回 第377(1962/10/10)号
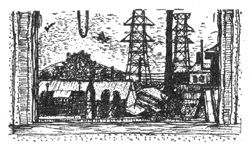
大学は何とか卒業したが、就職口もみつからぬままに、無給副手となって大学に残った。相変らず健康はすぐれず、勉強の方も何をやってよいか暗中模索状態が続いた。量子力学はその頃すでに建設が終り、いろいろな方面への応用の時代に入っていた。あらゆる物理の分野への応用が開け、毎月毎月現われる論文の数はおびただしいものであった。これら論文の洪水にまき込まれて、どちらを向いて泳いで行くべきか、ただアップアップする状態であった。湯川くんは、この洪水の中ですでに自分の進路を発見していたように見えた。すなわち、次にくるものは原子核と場の量子論であるという見通しを、そのときすでに立てていたように思われる。そして彼はこの方向に向って、着々と自分のペースで進んで行った。
彼とは同じ部屋をあてがわれていたが、彼は考えごとに熱中しだすと、机をはなれて部屋の中をぐるぐるとまわりはじめるくせがある。学問に対するこの傍若無人な集中ぶりは(ことわっておくが、傍若無人ということばの元来の意味は、かたわらの人を無視するような粗暴な行いをするということではなく、かたわらに人のいることも忘れるほど、何ごとかにうち込むことである。ということを漢文の先生にきいたことがある。ここはもちろんその意味である)大へんなものであった。しかし、今だから白状するが、このぐるぐる歩きは、かたわらに居た気の弱い人間にとってはいささか迷惑で、これが始まると、こちらはいらいらとしてくる。しかし、やめてくれという勇気もなく、こういうときには、こっそりと図書室へにげ出すことにしていた。これはいささか刺激が強すぎることであった。
湯川くんは、卒業して一年とたたない間にすでに自分の仕事を仕上げた。それはスペクトル線の超微細構造の理論というもので、原子核のスピンというものの影響でスペクトル線にどういう現象が現われるかという独創的なものであった。この仕事は後で、ノーベル賞をもらったイタリアのフェルミも手をつけて、湯川くんが論文をまとめ終る少し前に発表してしまったので、彼にとっては残念ながらプライオリティーを失う結果になったが、フェルミのような一流の学者と同じ仕事を独力でやってのけたことは、彼にとって大いに自信をつけることであったにちがいない。
湯川くんのこの勉強の進行ぶりに対し、自分は何とふがいないことだろう。不健康と無理な試験勉強ですっかり疲労困憊し、劣等感はますますつのるばかり、とてもそんなむつかしい分野に進める自分ではないという気もちはますます強くなる一方であった。
当時教室は農学部のキャンパスに移ったが、教室の前に七面鳥の飼育場があり、毎日々々、ホロロホロロ、という鳥の声が人を馬鹿にするように聞こえた。考えごとは少しもまとまらず、窓の外をぼんやりながめたり、これではいけないと思ったり、そして、何か自分でもできるようなやさしい仕事はないものかなどと考えていた。そして時には、物理学というものがあまりにも索漠としたもののように思われ、物理学的自然という乾ききった世界より、もっと美しく、うるおいと人間味のある世界こそ自分の生きるべき場所ではなかろうか、などと考えてみたりした。しかし、今さらせっかく始めた仕事を思い切る勇気も出ない。今やめてしまったのでは、今までの苦労が全部無駄になってしまうではないか。だから、とにかく何でもよいから、どんなつまらないものでもよいから、たった一つだけでよいから、何か仕事をし、そうしたら、そこでくぎりをつけて、あとは、どこかの田舎でささやかに余生を送ろう、などと本気で考えていた。
こんな暗い日が三年間ほどつづいたが、こういう状態からぬけ出させてくれたのは、仁科先生との出あいであった。
(カットは筆者自身による研究室の窓から見た構内のスケッチ)
第4回 第379(1962/11/10)号

昭和四年ごろ、京都の物理学教室にはただ一人、その論文が外国でも引用されるような研究をしておられる先生があった。それは分光学の木村正路先生であった。先生の専門は実験で、はじめは理論物理にはあまり同情的でなく、弟子たちが理論の本などを読んでいると、時間のろう費だとおこごとを食ったという話であったが、ちょうどその頃海外視察に出かけられ、新しい量子力学が怒涛のように全世界をゆさぶっている様子を見られ、日本でも何とかしなければこの大勢から落伍してしまうことを痛感されたようであった。そのころ、長い間海外にあって量子力学の建設をその目で見、またその事業の一端をみずから担われた仁科芳雄先生が帰って来られた。そこで木村先生は仁科先生を京都大学に呼んで、若い連中に対し量子力学の講義をすることを依頼された。
仁科先生の滞在は一ヵ月ほどであったように記憶する。しかしその短い間に先生のわれわれに与えた印象は実に深いものがあった。その講義は物理的肉づけと哲学的背景をたっぷりもったものであって、今までもやもやしていたことがらもそれを聞いたとたんに明確になる、といったようなものであった。それにもまして、講義のあとの討論は忘れられないものであった。
先生が外国で完成された有名なクライン・ニシナの公式というものについては、われわれもすでに学んでいた。このように、公式にその名前がつけられているような世界的偉人はどんな人であろうか、と若い学生は考える。しかし一方、そのような盛名は若い学生にとっては一種の圧迫感を与えるものである。特に劣等感になやまされていた学生にとって、先生に直接質問をしたり、自分の考えを述べたりすることは、思いもよらぬことであった。
しかし、仁科先生は世界的学者ということから連想されるカミソリの刃のような印象からは全く違い、温い顔つきと、全く四角ばらない話しかたをされるかたであった。その結果、何度かのためらいの後、そして大変な決心の後、講義のあとに質問や、こちらの考えなどを述べてみた。質問しようと思ってみたり、やはりやめておこうと思ってみたり、またそうしながらそんなにえきらない自分をはがゆいと思ってみたり、あとから考えると、自分ながら何と愛すべき若者であったことよと思われる。
仁科先生は、そのころ東京の理化学研究所に新しい研究室を作る計画を立てておられた。そして理論面での助手として、この京都で会った若者を使ってみようと思われたらしい。東京へ出てこないかそして自分と仕事をしてみないか、というお手紙がやってきた。しかし、何しろ田舎で余生を送ろうなどと本気で考えていた者にとって、これは全く力にあまる仕事のように思われた。理化学研究所は日本でも有数な学者の巣であって、そこには天下の駿才が雲のように集まっているので、とても自分のような能力のないものがその仲間に入れそうには思われなかった。
それでは、ためしに二、三ヵ月来てごらん、と仁科先生はいわれた。それでやればやれると思ったら決心はそのときでよい、ともいわれた。そこで、二、三ヵ月なら行ってみようか、と心が動いた。三ヵ月たって帰るときに、どうですずっとこっちにいませんか、といわれた。けれどもみんなここはすばらしい人ばかりで、僕なんかとても、ついて行けそうもないのです、というと、先生は、なに見かけほどではないよ、大した連中ではないよ、といわれた。
仁科先生とのこの交渉がなかったら、おそらく予定コース通り田舎で余生を送ることになったかもしれない。湯川くんのように早くから自分の進むべき路を見出すことができず、あれこれと迷っていたものにとって、それは決定的な機会であったと思われる。
(カットは筆者自身による「自画像」)
第5回 第380(1962/11/25)号
東京へ出て来た日は雨がしとしとと降っていた。いつもの悪いくせで感冒後の微熱がとれず上京の日がおくれて、やってきたのは五月はじめ頃であった。まだ熱はとれ切れなかったが、どうやら無事に東京へやってきた。知人の紹介で理化学研究所の近くの「旅館御下宿平和館」というところで下宿住いをすることになっていたが、門を入ると、玄関の前に大きなさるすべりの木があって、梢からは風がふくたびにパラパラと雨のしずくがおちていた。そのわきには鳥小屋があって、金網の中では、うすら寒い雨にしめった支那鳩が二、三羽とまり木に身をよせて丸くなっていた。
これからのわがすみか、六畳の小部屋はガランとして殺風景であった。窓の下の路はあちこち水たまりになって、夕方の光をにぶく反射して居り、玄関の方からはゴロボーゴロボーという鳩の平和な声がときどき聞えてきた。
あくる日も雨であった。熱をはかるとまだ七度二、三分ある。しかし、午後は雨もこやみになったので、あれこれと買物をするために上野に出かけた。松坂屋で机や書棚を買い、そのあと公園に入って西郷さんの高台から東京の町を見おろしたとき、これから何か新しい生活がはじまるかもしれないのだという感慨が急におこってきた。

研究所の仁科研究室はまだできたてであったので、仁科先生の居室と、中はまだがらんどうの実験室一つだけが決まった部屋で、あとは暫定的なかり住まいであった。あてがわれたのは雑誌のバックナンバーや紙型をしまっておく倉庫の一角で、そこに一人で閉じこもることになった。ひる間でもときどき鼠があらわれて、黒い丸い目で不思議そうに妙な新参者をながめている。そんなところで仁科先生からあてがわれた仕事を始めることになった。
先生は毎日一度はこの奇妙な部屋に現われて、どうなりましたか、と仕事の進みぐあいを問うて行かれる。そして事こまかに指示、注意を与えて帰って行かれる。ときには、土地が変って病気したりするといけないから気をつけなさいよ、などといわれたりする。
まだ誰も友だちができないので一人ぼっちの感じであった。もともと人みしりのくせがあったので、こちらから友だちを求める勇気もなかった。ひるの食事もこの部屋で一人配給のコッペパンですませた。帰るときパンの残りを机の下に置いておくと、夜の間に例の鼠がきれいにかたづけてくれた。
夕方下宿に帰り晩めしをすますと、あとはすることがないので、よくぶらぶらと町を散歩した。五月から六月になり、そろそろ夏が近くなると、夜の町には蚊やりのにおいがただよい、店からのぞかれる家々の中で、子供たちが夕飯をたべ、おやじさんが裸で晩しゃくをやっていたり、母おやが赤ん坊をねかしつけていたり、そんな光景が見えた。日曜日には、天気のよいときは郊外散歩に出かけたり文庫本を買って近所のお寺の墓地の石にこしかけてそれを読んだり、また、町の空地で人たちが草野球をしているのを見ていたり、そして見ている人々をこっそり写生してみたり、そんなことをしているうちに仕事の方も少しずつ進んでいった。
こんなぐあいで試験期間の三ヵ月がすぎて、いよいよ正式に研究所に就職するかどうかを決めるときがきた。とても東京の連中にはついて行けないような気が相変らずしている。仁科先生は、そんなこと君なら大丈夫だ。と言われるけれど、そんなに信頼されればされるだけ、それを裏切るようなことがあってはならないように思われる。そこで、とにかく一応京都に帰ってゆっくり考えさせて下さい。と先生にいうと、先生はこころよくそれを諒承して下さった。
しかし、実はそのとき、かなりはっきりと決心はついていたように思われる。その証拠には机も書棚も夜具ふとんも、御下宿平和館に置いたまま、部屋も解約しないままで帰洛したのである。
(写真は仁科先生来講の時の記念写真)
第6回 第382(1962/12/25)号

夏休みのあいだにいよいよ正式就職の決心をつけて、九月にはまた「御旅館平和館」にもどってきた。初任給六十円、それで下宿代そのほかの費用を差引いてじゅうぶん余るという結構な身分になった。神田の学生街で型の如くセザンヌやゴッホの複製を買ったり、露店で観葉植物をもとめたりして、まず平和館の小部屋を少しは人間のすみからしくととのえ、またワイシャツやネクタイなども一応とりそろえて、人なみのおしゃれもすることにした。
そのうちに研究所の空気にもだんだんなぢんできた。この研究所で驚いたことは、その全く自由な空気である。先生たちも若いものも、お互全く遠慮なく討論するそのありさまである。それからまた東京の連中の頭の回転の速いことである。ゼミナールは、この遠慮のない、血のめぐりの速い連中の形式も儀礼も全くない討論で、生き生きと進んでいく。中でも、今では原子力研究所長におさまっている菊池正士さんとか、埼玉大学長になっている藤岡由夫さんとかいう駿才は、無遠慮さにおいてその雄たるものであった。
この生き生きとした空気の中で、京都時代の重くるしい気分は、一枚一枚うす皮をはぐようにとれていった。健康も少しづつよくなった。そして友だちもだんだんにできてきた。
研究所には、よく学びよく遊ぶ連中が大ぜいいて、アルコールの味や、寄席の妙味、ハイキングその他、演劇や音楽を鑑賞する楽しみ、そんな一般教養を京都出の田舎者にしこんでくれる有能な先生がたには事欠かなかった、中でも今横浜大学にいる竹内枢くんというちゃきちゃきの江戸ッ子は、研究室にぽっかり現われた珍らしい上方人種に大いに好奇心をよせ、それに江戸的教養を授けることに特に熱心であった。
理化学研究所はその名のように物理と化学の研究が中心になっている。その中で、物理部門は金を使う一方であるが、化学部門ではビタミンの発見で有名な鈴木梅太郎先生をはじめとし、いろいろな薬品の発明などで収入の方に一役買っていた。また薬品のほかに合成酒の発明なども化学部門から出ていて、地下室の倉庫にいくと、実験用のガラス製品、試薬類、文房具などのほかに、ビタミン剤や合成酒なども売っていた。そこで勉強につかれるとビタミンを買ってのんだりする一方、合成ウイスキーを買ってきて、こっそり机の中にしのばせておいたりすることをおぼえた。このくせは教育大の学長になってもぬけず、学長室の戸棚の中には、いつも同様の品物が鎮座ましましていたものである。
そのうちに仁科研究室もだんだん充実してきて、実験室には宇宙線研究用の装置などがととのってきた。ガイガー計数管を宇宙線が通るたびに、サイラトロンという真空管が青く光って、記録装置がポツリ、ポツリと下手なタイプを打つときのような音をたてていた。
こんな装置は今からみると全くおもちゃのようなものであったが、それでも当時は日本のどこにもない最先端のものであった。そして京都の連中などが時たま研究所をおとずれると、門前の小僧よろしく、聞きおぼえの実験的知識の受売りをして得意になったりした。そのありさまは、丁度自分のうちの最新式のおもちゃを得意になって友だちに見せている子どもそっくりであった。
研究室が充実するにつれて人員も増えてきた。一年後には理論の方にも、先ず京都大学から今は名大教授の坂田昌一くんがやってきた。彼は一年だけの滞在であったが、その次の年からは小林稔くん(いま京大教授)、玉木英彦くん(東大教授)が正式に入室した。小林君は平和館に居をかまえたので、彼とは朝から晩までのつき合いであった。晩めしを下宿ですませたあと、また研究室に出かけて一しょに夜なかまで勉強したり、日曜日には一しょにハイキングに出かけたり、寄席のつき合をしたり、一しょに飲んで肩くんで町をあるいたり、あまりいつも一しょに居るので、時にはお互顔を見るのもいやになって、つまらないことでケンカをしたり、そうかと思うと一人が何かの用でどこかへ行ったりすると、さびしくてしかたがなかったり、思えば若い者同志の友達づきあいの心理というものは誠に妙なものである。
(カットは筆者自身による「御旅館平和館」)
第7回 第383(1963/1/10)号

仁科研究室ができた昭和六年から七、八年にかけて、原子核物理では次々といろいろ重要な発見があった。陽電子とか中性子とかいう新しい素粒子がみつかったり、粒子加速装置を使って原子核破壊をする実験がはじめて成功したりした。また、今まで雲をつかむようだった宇宙線の本体も、次から次へと見つかった珍しい現象から急に明かになってきた。
こういう情報が欧州からアメリカから伝わってくるたびに、理化学研究所のゼミナールの空気は一種熱っぽくわきたった。実験の連中は、何とかして日本でも加速装置を作り原子核を破壊してみようと考え、理論の連中は、新しい素粒子の性質を理論的に解明しようと大いに研究意欲をもやした。
ゼミナールでは、核破壊の論文の出ている「ロンドン王立協会議事録」を前に皆が顔をつき合わせて、その装置がどんなものであるか、いろいろ検討をはじめた。しかしこの記録だけではよくわからない。何時間も何時間も、ああでもない、こうでもない、と論じあうありさまは「原子核物理学ことはじめ」とでもいったような光景であった。
陽電子という粒子は宇宙線が物質を通るときに作られるものである。これに類する粒子の存在はイギリスの天才的理論物理学者ディラックが予言していたことであったが、陽電子すなわちディラック粒子であるかどうかということはディラックの理論を使って粒子発生の頻度を計算し、それが実験と合うかどうかをあたって見なければ窮極的には結論できないことである。そこで仁科先生はこの計算をやろうではないかと指示された。
この計算は相当手ごわいものであって、どこから手をつけてよいかわからないような難問であった。何度も仁科先生と討論して、一応のプログラムを立てては見たが、果してうまくいくか一向自信はなかった。そうこうするうちに昭和八年の夏休に入った。しかし外国でもこの計算をやっている者が居るかもしれないので、先を越されないために、夏休を返上してがんばることになった。
それにしても東京の夏は暑すぎる。仁科先生は御殿場の東山荘というYMCAのホステルに目をつけられ、丁度研究室にきていた坂田昌一くんも加えた三人でそこに合宿して、この仕事に取っくむことになった。
東山荘は乙女峠のふもとにあって、一種の大きな山小屋とでもいったほうがよいようなところである。暗く繁った桧林をぬけると、急にあかつめ草など生えた少しあかるい草地へ出る。そこには大きなサイカチの古木があって、その向うに明るい芝生がみえる。これが東山荘の前庭である。部屋に案内されると、窓の網戸を通して、よくしげった桧林、その黒っぽい木だちをすかして向うの草山の新鮮な緑の光が見え、鶯の声がしきりにきこえてくる。そんなところである。到着したのは夕方であったが、一休みしているうちに夕食の合図がなる。食堂へ出ていくと芝生で遊んでいた男女の若い連中もぞろぞろ集まってくる。お互いに自己紹介などしているうちに電灯がついて、食堂は急に花やかな空気になってくる。食後芝生に出てみると、サイカチの向うには、うす白い光がみなぎっていたが、それは貯水池であって、その堤からうしろ山にかけて雲がひくくたれているのが見え、風が渡ってきて寒いくらいであった。
部屋に帰って夕やみの中で荷物を整理し、いよいよあしたから仕事に取りかかる大切な商売道具、計算用紙や鉛筆などを机にならべ終って、おりたたみ式のヅックのベッドにころがってしばらくじっと天井をながめていると、何の音もきこえない窓外から網戸を通してひんやりとした夜気が流れ込んでくる。裸電灯のあかりをつけると、部屋の中に大きく影法師が動いてあかるくなり、しばらくすると網戸の外にたくさんの蛾が羽ばたきしてぶつかってくる。こんなところがこれから一仕事をするわが山小屋の一室である。
一応のプログラムは立てておいたものの、一向にうまくいきそうになかった。あの手この手とやっては行きづまり、とてもだめだと思うことも何度かあった。そうして、何日か無駄な日を過したある日、計算式の中に、省略しても答えに大して、ひびかない項のあることに気がついた。そこで、こういう項を一応ないものと考えてやればうまくいくのではないかという気がした。この考えを仁科先生に話すと、先生は、それはいい考えだ、是非その方法で計算を進めてみるように、と励まして下さった。
(写真は「仁科賞盾」)
第8回 第386(1963/2/25)号
一応計算の方法がきまってみるとそのやりかたで仕事を進めるには持って来た参考書は全く役にたたないことがわかった。そこで一度東京に帰って、必要な本をリュック一ぱいかつぎ込んで来た。今でもおぼえていることは、その本の重かったこと、駅の階段のシンドかったことである。
これらの本と首っぴきで毎日毎日計算を続けた。数式は、始め手のつけられないような複雑なものであったが、予想した通り一つ一つ不思議なくらいきれいな、そして簡単な形にまとまっていく。何ともいえず快調である。
この御殿場の山荘での仕事は、夏休みの終るころには、一応のメドを立てるところまで進んだ。ここまでくれば、あとは、まあ、順調に進むという段階までこぎつけることができた。そこで計算の結果を持って九月には東京へ戻ってきたが、そのときのなんともいえない満足感、あんなに困難にみえた仕事が、自分のようなものでもやれたのだ、という自信感、これは生まれて始めての経験であった。
東山荘では仕事も楽しかったが、そのあいまあいまの生活も今までに経験したこともない楽しみにみちたものであった。毎朝四時頃には、ヒグラシが一せいになき、それにつづいて鶯が歌い、その声で目をさまして窓をあけると、朝の爽快な空気がサッとばかり流れ込んでくる。
そこで、ひと思いに起床して、ひとり散歩に出かける。廊下には、まだねぼけたように鈍い電灯がついていて、そこには無数のガが死んだように動かず眠りつづけている。外はうす暗くて、朝もやの中から貯水池だけが白っぽく光ってみえる。そんなところを通りすぎて、時には朝食前に乙女峠まで足をのばすこともあった。朝もやの上限をすぎると、急に、おりから出たての朝日をあびて鮮やかな色を呈している赤富士が、目ざめるばかり晴れわたった青ぞらの中にくっきりと浮び出て、その中腹には丁度土星の輪のように、白い輪ぐもがからんでいて、山はだにじっとその影を投げかけている。そんな光景の見られることもまれではなかった。
また、午後の休み時間には、芝生で若い連中とクロッキーという遊びをしたり、下手なソフトボールの試合をやったり、夕食後は中学生、女学生たちを集めてお正月のようにたわいもないゲーム遊びをしたりした。日曜日には、食べものをしこたま用意して、ちかくの山や谷にピクニックに出かけたりしたが、こんなとき、女性の加わるということが如何に空気を花やいだものにするか男女非共学時代の悲しさ、そのとき始めて経験したものである。
御殿場から持って帰ってきた満足感や自信感は、しかしながら長つづきはしなかった。外国でも同じことをやっている人たちのいることがだんだんにわかってきた。しかも、こちらが仕事をしあげる前に、それらの論文が発表されてしまった。それだけならまだよいが、その論文の完ぺきさ、われわれの仕事よりはるかに巧妙にかつてってい的にやってあるではないか。
こうなってみると、あれしきの成果に得意になっていた自分のつまらなさが骨身にしみて感じられる。自分のような非力なものが、いくら精魂をかたむけて何かやってみても、結局それぐらいのことは、もっとえらい学者がどこかでやってしまうのだ。そうなってみると、自分の存在に一体、何の意味があるのであろう。自分のようなものはいてもいなくても、学問の進歩に何の影響も与えないのではないか。
けれども、こんなことをいっていても始まらないので、なかば気持をまぎらすつもりもあって、意味があろうがなかろうが、とにかく関連のある仕事を馬車馬のように続けることにした。しかし、それらも一応結果がでる度毎に、外国で同様の仕事が発表され、いつもいつも後手になる。こんなことを一年間ほどつづけたあげく、見出したものは再び完全に疲労困憊した自分であった。
第9回 第388(1963/4/10)号
御殿場へもう一度行ってみよう。今度は仕事など一切しないで、朝から晩まで遊んで暮そう。そうすればまた元気が出るかもしれない。そんな気もちで次の夏も東山荘へ出かけてみた。しかし仕事がなければないで心は滅入るばかり、うわべは楽しそうにしていたけれど、自分はつまらない無用者なのだ、自分のようなものが大それた学問などやろうと思ったのは結局やっぱりまちがいだった。といった想念がいつも心の底にこびりついている。そんなとき、東山荘の朝の礼拝から聞えてくる讃美歌の甘美な声に意味もなく涙ぐんでみたり、そうかと思うと、その礼拝の蜜豆のような甘いだけのムードに反発を感じてみたり、そして、あたりの自然がみずみずしく美しければ美しいで、物理学的自然などという灰色の世界をいじくりまわすことの何と空虚なわざであることよ、などと言いたくなってきたりする。しかしそれと同時にこんなことを言う自分が、イソップの「すっぱい葡萄」に登場する狐のようにひねくれた人間に見えてきたりする。

昭和十年ごろから理化学研究所のようすが少しずつ変ってきた。いろいろな発見から物理学が原子の世界から原子核の世界に入りこんできて、研究所でもそれに応じた再編成が必要となりつつあった。物理学の中心はそれまで分光学とかX線の研究にあって、研究所でもこの課題にとりくむ研究室が多かったが、それらの研究室の中からも原子核物理の方に転向を望む声が出てきた。そういうわけで、研究所体制をある程度修正する必要が起ってきた。
原子核物理の研究には今までにない大がかりな装置と人員とが必要になってくる。つまり、それまでの研究所体制ではあまりにも単位が小さすぎるという実情が現われてきたのである。そういうわけでいくつかの研究室が共同して大がかりな研究を進める方針がだんだんとられるようになってきた。
このように研究単位がだんだん大きなものに総合される一方、専門的には逆に分化の現象が起ってきた。実験装置が大きくなってくると、それを作るにも運転するにも、実験家は全力をそそがなければならなくなる。また理論の方もその分野でしなければならない仕事が山のようにでてきて、到底他のことを考える暇がなくなってくる。
こういうわけで、それまでは理論家と実験家と、またいろいろちがった専門の人が一しょになってやってきたゼミナールも、それぞれ専門別に開かれるようになってきた。
今までのゼミナールには色んな人がやってきた。東大からは小谷正雄くん(現東大理学部教授)、犬井鉄郎くん(東大工学部教授)、永宮健夫くん(現阪大教授)たちが常連であって、これらの連中からはいわゆる物性論の話がきけた。しかしゼミナールが専門的に分化するようになってからは、これらの人たちの話はきけなくなってしまった。それはある意味でさびしいことであったが、やむをえないことでもあった。
原子核物理の大装置を作る仕事は当時として大変なことであった。何しろ日本の低い工業水準では、設計から強度試験まで殆んど自分でやってみなければならない時代である。金をあつめ、メーカーとの交渉、これも大変な仕事である。そして、こういう仕事に仁科先生はその勢力の大きな部分を使わねばならぬわけであるので、おのずから前のように細かい指導をわれわれに与えることができなくなった。仁科先生は弟子たちを理論、原子核実験、宇宙線実験の三つのグループにわけ、みずからはもっぱら実験グループの陣頭指揮にたち、理論の方は朝永くんにまかせる、ということになってしまった。
こうなってくると、もはや自分は無用者なのかどうか、などとハムレットみたいなせりふを言っているわけにはいかない。有用であろうが無用であろうが、また、空虚感があろうがなかろうが、研究室みんなの車が動き出したのに自分の車だけまごまごしているわけにはいかない。
(写真は理化学研究所)
第10回 第389(1963/4/25)号
お前は物理が心から好きなのだろうという質問をよく受ける。考えてみると、大学を出てから三十年以上も物理で飯を食ってきたわけだから、きらいだったとは言えないかもしれない。しかし、寝食を忘れてそれにぼっとうしたとか、研究に一生の情熱をささげたとかいった、えらい学者を形容するおきまりの文句はおよそ使えないように思われる。
たしかに、仕事が快調に進んだときは、ある程度夢中になったこともある。しかし、そんなことは十に一つ、あと九つは途中でいやになったり、何の因果でこんな商売をやらねばならないかと思ってみたり、三十年というのも結局こんな状態のくりかえしである。仕事が予想通り行ったときはうれしかったものだが、大部分は予想はずれで、幻滅の悲哀をなめるばかり、それが習い性となって、何をやるときも、熱っぽいうちこみ方などできるものではない。
仕事がうまくいったときのよろこびも、考えてみれば、純粋な真理追究のよろこびではなかったようだ。そこには功名心という雑念が入っている。また、本当に学問自身にうち込んで、真理自体を知ることに幸福を見出すのなら、誰のやった発見でも、それを学ぶことに無上のよろこびを感じるはずである。ところが実際はそうなっていない。今だから白状するが、湯川理論ができたときには、してやられたな、という感情をおさえることができなかったし、その成功に一種の羨望の念を禁じ得なかったことも正直のところ事実である。
ほんとうのえらい学者はこんな雑念になやまされることはないはずだ。それにくらべて、まるで邪念妄想のかたまりのような自分の何とつまらない者であることよ、こんなことをくりかえしくりかえし考えたものである。
だんだん年をとってくると、修養がつんだとでもいえるのであろうか、このような雑念は次第に起らなくなってきた。しかし、悲しいことに、それと同時に、研究に対するファイトも、とみに弱くなってきた。だとすると、これは修養の結果ではなく、ホルモン減少の現われであるのかもしれない。人間の円熟などということは、万事につけこんなことかもしれない。さびしいことである。

さて、仁科研究室もだんだん大きくなると古き良き時代も少しづつごたごたしてくる。人間関係も複雑になり、研究室の中に不平不満の空気がただようこともあった。「原子核物理ことはじめ」の時期には、いろいろ困難があっても、夜がしらじらとあけはじめるあけぼのの楽しさがあった。それから小さいサイクロトロンという機械をみんなで作り上げ、それが運転しだしたとき、みんなは将来への期待に胸をふくらませた。しかし仁科先生の野心はこれでおさまらず、もっと大きい、当時にしては世界最大の機械を新しく作る計画がでてきた。この仕事は困難を極め、実験の連中の苦労はなみたいていのものではなかった。あとでわかったことだがこの機械の設計には重大な誤りがあったのだが、それがわかるまで、実験の連中がいくら努力してもうまくいかない。さすがの仁科先生もいくらかあせりがあったようで、それが実験の場に微妙に反映し、こんな困難な仕事に時間をつぶし、何の成果もあがらぬより、もっと容易な道で研究を進める方が賢明ではないかという意見の者も出てくる。こんな考えで仁科先生のもとから離れていった者も二、三人はいた。
理論の方にはこんな問題はなかったが、それでも不平がなかったわけではなかった。それは、何か仕事をしあげて論文にまとめても、仁科先生はそれを手もとにおいたままいつまでも出版しないことである。こんなことで外国の学者にプライオリティーをとられてしまったことも二、三回にとどまらなかった。そんなわけで時々は仁科先生に反抗してみたり、以前のように先生一辺倒ではなくなってきた。しかしそれでも先生の魅力はまた別の話で、よく反抗期とか精神的離乳期とかいわれるが、そういう時期の子供のように、先生に対する甘えと反抗心の奇妙な交錯の時期であった。思えば仁科先生からの精神的離乳期である。
(写真は理研の小サイクロトロン)
第11回 第390(1963/5/10)号
この辺で中間子論が出たころの思い出話にうつろう。昭和八年ごろ原子核が陽子と中性子でできているという有名なハイゼンベルクの論文が出た。ハイゼンベルクの考えによると陽子と中性子の間には強い力が働いていて、それが原子核というかたまりを作る原因になっている。そして原子核の中で陽子は中間子に中間子は陽子に変化することができ、例えば中間子が陽子に変るときには電子が核から放出され、これがベータ線となるという。
ハイゼンベルクはこの考えを定性的に述べただけで、それ以上発展させなかったが、湯川くんは先ずこの考えに基づいてベータ放射能の理論を作り上げようとした。しかしこれはなかなかうまくいかない。妙な矛盾するようなことばかりでてくる。そこで彼も手をやいているうちに、イタリヤのフェルミが美事に理論を作り上げた。中性子が陽子に変るときには電子だけではなく質量が殆んどゼロのいわゆる中性微子という粒子が一しょに出ていると仮定すれば万事うまくいくのだが、湯川くんはこの考えに気がつかなかったのである。
しかし彼はここでガッカリしてなげることはしなかった。次に彼の考えたことは、このフェルミの理論に基づいて、陽子中性子間に働く力の原因が説明できないかということであった。この考えは何も湯川くんのものだけでなく、海外でも二、三人が考えたことであったが、これも結果は失敗であった。この考えかたで出てくる力は何とも弱いものであって、ハイゼンベルクの考えたような強いものではなかった。
多くの人はここであきらめてしまった。この力の原因の問題はおそらくもっと遠い将来にはじめて解決されるものであろうという考えかたである。しかし湯川くんはここでおそろしく大たんな仮説を提案した。それは、電子よりはるかに重い未知の粒子があって陽子が中間子になるときにこの粒子が、間接にではあるが関与しているという考え方である。そして、もしエネルギーが十分に与えられれば、実際にこの粒子も核の外にとび出してくるであろうと予想をたてた。
いつのことであったか忘れたが、東北大学で物理学会があったとき、彼はこの着想を運動場の地面に木切れで式を書きながら語ってくれたことを覚えている。「強い力の説明はできたが、けったいな粒子が出てくるわ」といった彼のことばを今でもよく覚えている。この「けったいな粒子」が実さいの実験でみつかったのはこのときから二年ほどたってからのことであった。
思えば彼のこの成功は大変な刺激であったといえよう。してやられたと思ったことは前に白状したが、いつまでも仁科先生の番頭役ばかりしてはいられないぞ、という考えの出てきた大きな動機だったことも事実である。
しかし、こうやって少し力んでみた時分に健康状態が悪くなってきた。医者のすすめで少しのんびりしなさいというわけで、平和館という古巣を引あげて、千葉県の市川に引越した。市川といえば今は立派な都市だが、当時はこやしくさい田舎であった。そこで一年近くぶらぶらして、理化学研究所には週に二、三回顔を出す程度、あとはうちで本をよんだり、散歩したり、というのんきなようだが、やはりこんなことをいつまでやっていてよいだろうかとなやんでみたりしていたがどうも病気には勝てない。
そうしているうちに昭和十二年にドイツへ留学することになった。健康も先ず先ず回復し、四十日のインド洋航海をへてナポリに上陸し、そこからハイゼンベルクの居たライプチッヒについたのは六月の末であった。胸をふくらませてドイツに留学、と言いたいところだが、どうも前途に何か大きなことがひかえている、などという予感も期待も何もなかった。そして来てみれば言葉は通ぜず、心細いばかり。ハイゼンベルクの教室には、その二、三年前までいたそうそうたる連中はみなナチに追われ、そこに居るのはまだ学生あがりの若い連中ばかり、従ってゼミナールも程度がひくく、どうも期待はずれの感がかくせなかった。
第12回 第392(1963/6/10)号
ライプチッヒ大学には日本学という学科があって、日本の文化に興味を持っている学生が何人かいた。そういう連中と日本人留学生とが一しょに生活することが相互理解を深める役に立つというので日独学生ハイムという寮があった。ここでの生活経験は今思い出しても興味深いものがある。
ドイツの学生生活というものは一種独特の味のあるものだが、何しろ日本文化に興味を持つといった連中のことだから、通例のドイツ人の学生とはまたちがった気風があり、ドイツ流のギコチないアカデミズムを馬鹿にしたような、またドイツ人にありがちな肩ひぢ張った議論のやぼったさがおかしくてたまらぬといったようなヘソまがり、その代りいつまでたってもドクトル論文ができないといったような、そんな愛すべき非秀才たちがこの寮に集まっていた。そういう連中と二年ばかり一しょに暮すことになった。
海外留学というものは専門の勉強もさることながら、いろいろ得るところの多いものである。一つは専門の異った留学生同士の接触によって、今のことばでいう一般教養を身につけることができること、もう一つは外人とのつきあいで人種や国籍を越えた相互理解の得られることである。特に学生ハイムといったところでこれらの友人たちと起居を共にするときこの効果は倍増する。
こんなわけで、ドイツの若い学生たちと、われわれ留学生の間にも一種の淡淡とした、しかし味わい深い友情が生れてくる。特に、ナチ政権下でドイツの学生たちのもっているいろいろな悩みが、彼らは口に出してこそ言わないけれども、われわれに何となしに通じてくる。彼らが日本学などを専攻にしたのも、何とかして、彼らからみて異質の文化の中に一つの救いを見出そうとしたからであったように思われる。当時日本もだんだんに暗い路をたどりつつあったわけで、彼らのこんな心境も、何となしにわれわれにもひびいてくるのである。
あとで知ったことであるが、このときの仲間たちの殆んど全部は第二次大戦で戦没してしまった。一しょに東西文化とか、哲学芸術などについて論じたり、詩の朗読をしたり、タキシードなどでメカシ込んでパーテーに出かけたり、またビールを飲み合ったり、旅行をしたりした彼らはいま殆んど一人も生きていないのである。
さて、そこでこれからその二年間の思い出ばなしになるわけだが、昨年学長をやめてやれやれと思い一いき入れた幸福な時間もたった半年でだめになり、今度は学術会議会長という世界一うるさく面倒な仕事をおっつけられてしまった。何とも世の中は思うようにいかないものである。
そんなわけで、この原稿を書くひまもなくなってしまったが、幸にその当時の日記があるので、それを引っぱり出して、そのまま思い出ばなしに代えることをおゆるし願いたい。少し木に竹をついだような形になるが、このへんでおもむきを変えるのも案外一つの手かもしれない。
滞独日記
(注・日付は原文では漢数字で書かれていますが、読みやすさを考慮し、ここでは算用数字に改めました。)
第13回 第394(1963/7/10)号
1938年
 4月9日
4月9日
今日は朝天気だと思ったのに曇りだしときどき嵐になり、雪が一面にふる。計算のチェックをする。ひるから映画にいく。町は相当の人出。そのあと、火の玉亭(フォイヤクーゲル)で晩めしを食う。ここは給仕のねえさんがいるところで、日本のねえさんと同じ気分がする。帰ってヒットラーのラジオをきく。オーストリア合併で、町は家々の窓にろうそくをならべ、お寺の鐘がなり、飛行機がたくさんとぶ。
4月13日
学校へ行って講義をきく。それがすんで十一時ごろハイゼンベルクの部屋に行って、ぼくの仕事を書いたものを渡す。彼は読んでおくから一週間後にそれについて話をしようということになる。大変長い計算を大変だったろう。読ませてもらって色んなことを知ることができてありがたい、などと彼はお世辞をいう。しかし、こちらはこのころ何やかやで微少妄想をおこしているから少しもうれしくなく、彼は定めし読んで、何だ、つまらなかったと思いはしないかという気がしてくる。
4月17日
ひる、火の玉亭でめしをたべる。Nとだべる。彼は前途の抱負をのべる。彼は実に純真な哲学青年である。
4月21日
ハイゼンベルクの部屋に行く。ぼくの仕事を読んで批評してくれる。テキストをもう少しくわしく、たくさん書けといわれる。物理の論文で大事なところは、数式よりもむしろテキストにあるし、人の読みたがるところもテキストだといわれる。ハイゼンベルクはお世辞がいいけれども、これくらいの学生のような仕事では、ぼくは情けない気がしている。そうしてドイツに来ても研究室の連中となかなかなじめないで、人みしりばかりする自分を悲しんでいる。
4月24日
Nにいろいろの話をきく。エロス、フィリヤ、アガペ、などということ。ダンテの神曲のこと。それからキリスト教のこと。ロマン主義哲学のこと。ぼくはいい友だちができたことをうれしく思っている。
4月30日
今日も結局、何もしないようなものだ。このごろ、いかにも理屈に合わない気分がぼくの行動を支配している。その気分の根本は時間のたつのをおそれるということらしい。それが妙なことに、だから何もしないでいた、というふうに作用する。何かすることによって、せっかくの時間が消えてしまうような気がするのだ。つまり、何かをやることによって「時間のたつのを忘れる」ことがいやなのらしい。
5月3日
ゼミナールはオイラーが宇宙線の話をする。湯川理論とよく合う由。夜、Nと芝居に行き、シラーの「たくみと恋」を観る。
5月14日
天気になって、鳥が朝四時ごろから鳴いている。フリークの花が咲きだした。外をあるくと、あついくらいになる。勉強心は一向おこらない。日光の中でぼんやり自然の中にうごくものを見ていたりするのが一番いい気もちである。本を読んでみても、とりとめもない空想の、ただの言葉のくりかえし、が頭を往来するだけだ。ひるから仁科先生に手紙を書き、床屋に行き、公園をあるく。夜、満月がでたのを見ながら、ドレスデンからのラジオをきいているうちに月は中天まで上った。
5月15日
今日から朝めしは中庭にむいたバルコンで食うことになる。夕方、食後、バルコンにいる。中庭の空をつばめがしきりにとんで、黒つぐみが歌う。この学生ハイムに同宿のドイツ人学生レクレムとボーマンとが歌を歌う。あまりに大声を出して寮母のヘルメッケ小母さんにたしなめられる。夜、Nに借りてきたパスカルを読む。人間についての考察という本。
5月18日
雨ふり。学校をさぼってパスカルを読む。十一時(夜ではない、朝の)ごろまで読むとねむくなる。そこで十二時までひるねをする。それから Physical Review を取上げたが、とりとめもない考えがおこるのみ、自分で何をしようとしているのか判らない。ハイゼンベルクの Explosoim から近似を進めて、原子核の部分的熱せられをやったらと思っているらしい。ひるからは又とりとめなく考えたり、外を見たり、そうかと思うと文芸春秋を読んだりする。雨がやんで夕方晴れる。そうすると空気がつめたい。
6月6日
夕方、また公園に出かける。日が下るに従って空気がつめたくなる。エルスター川のところはぼだい樹が青々としてその向うから月が出てくる。競馬場の入口が電しょくされ、きらめいている。やたい店が帰るしたくをしている。行きちがいざまにヒネーゼとののしる人がいる。夜、レクラム、ミューラー、ウエルナーの学生たち、N、だんだんと外出して学生ハイムの中は静かになる。
6月11日
外人クラブの夏祭りに行く、アウエン湖の遊園地であった。ホール一ぱいのダンスでいもを洗うようだ。ギャラリーのバーでO、レクラム、ミューラー、ボーマンら下宿友だちとコニャックをのんで、下でおどっている連中をみている。この若い学生らは、ダンスなんかはおかしくて、という顔でのんでいる。外は月が出ている。ぼくはそこのバーの高いイスにこしかけて、そこにいるドイツ人の奥さんとしゃべっている。ドイツ語でくだがまけるから妙だ。トモサンという僕のあだなを人々がおぼえて、トモサン、トモサンとみないう。
6月12日
フツカヨイ。夕方ふろに入ってベットにころがって外の雨をきいているうちに、なおってくる。何となく心がうるおってきて、人恋しい気もちになってくる。少しばかりエロス的な気もちになってくる。
(写真は朝永教授)
第14回 第395(1963/9/10)号
6月13日
朝めしの後、バルコンから中庭をみおろしていると四階下の中庭は二十けんばかりの家にかこまれて、中にいろいろな木がはえている。鳩の巣ばこのように裏窓がならんでいて、むこうのうちの窓にミシンをかけている少女や、せんたく物をひろげている女がいる。下の庭に草花の種をまいているおばあさんがいる。それらをみていると、池のふちから水の中をのぞきおろしている子供のようだ。木の葉が風にゆれるのが藻のように思われ、人々が魚のように思われてくる。
6月30日
ゼメスター(管理人注・学期)終りで、ゼミナールのあと、夜、大学でポーレの会がある。ハイゼンベルクのあいさつがあり、オイラーがドクトル・ハビルに、パッゲがドクトルになったおいわいをいう。また極東からきたお客さんが、一つの論文を仕上げたお祝いをいう。ぼくの論文のことだ。例によってお世辞がよい。その次、教室の連中はピンポンをやり、ポーレを飲む。ハイゼンベルクもピンポンに加わる。
7月4日
ハイゼンベルクに会って、論文を Zeitschrift für Physik に送る手つづきをすませる。この次はどういうことをやったらいいか助言することがあったらいってくれとぼくがいったら、あなたは自分で十分問題をさがす力があるのだから、ひとつさがしてみたらよかろう。何か具体的のことをやろうということになったら、いつでも相談にのる、という。インドから来ている若い学生ディッタが計算ができないとなげいている。そしてぼくに助力してくれないかという。その計算はハイトラーとベーテのやつだ。陰徳あれば陽報あろうかと助力しようといったが、なかなかやさしくない。
7月9日
ここはテューリンゲンの森の間の小さい村で、森は針もみで、谷間は青々とした牧草地である。ガラスを吹く工場がその青野のまんなかにあって、ガラス炉の煙突からたえず煙が立上っている。その谷間を軽便鉄道でやってきた。村の名はシュミーデフェルト、宿は村のはたごや。太陽館(Gasthaus zur Sonne)という。W夫妻がさきにきて部屋をとっておいてくれたのだ。
夜、はたごやの食堂でビールを飲んでいると、村の若い十五、六才の少年と少女とが十人ばかり集って社交を楽しんでいる。彼らは仲間の一人の少女がアメリカにいくのを送別しようとここに会合して、ブドウ酒をのんでダンスをしているのである。まだダンスのしかたも子供らしく、ブドウ酒で少し赤らんだ、うぶ毛の顔をよせながら、いかにも社交のはじまり、恋愛のはじまりのようにおどっている光景はまことに美しい。ヴェデキントの春のめざめの情景だ。ブドウ酒をのむにつれて彼らは歌いおどるが、歌声は少年少女らしく息が弱く、おどりはいつも少しはじらいを含んでいる。音楽が始まると少年がたって少女の前におじぎをして、一人へり、二人へり、とおどっていくのである。
十一時にねどこに入ると、階下の音楽は一時ごろまでつづいて、そこではたりと終りとなった。それから、あけがた、甘くエロス的な夢をみた。
7月10日
朝おきて便所にいくと、うしろで怪声がきこえる。野羊が戸のところで声をたてているのである。便所は野羊小屋につづいているらしい。さて、少し雨ぎみで雲が去来するが、森の方にいく。青い牧草地の中に細いすんだ水が流れていて、アルガルテの白い花、まつむし草の柴の花、つりがね草の青い花が点々としている。森に入ると木の間から牧草地の光がすけてみえる。
宿の主人は少しずるさを含んだ好人物で、しょっちゅうおかみさんにしかられている。大変なかかあ天下だ。
第15回 第397(1963/10/10)号
 7月16日
7月16日
水浴場の方へ行ってみるが、だれも泳いでいない。少々むしあつく曇っているが、時々陽がもれて牧草地には乾し草が蒸れたにおいをたてている。森をぬけるとまた牧草地があって、そこにすわっている。陽があたってくる。水が野のまん中を流れている。ぼんやりと、とりとめのないことを考える。青野の色や乾し草のにおいや、水の音が心の中にとりとめのない表象をよびおこし、それがからくさ模様のように頭の中を流れていく。さて起きあがって、帰り途につく。森のところにくると、首にベルを下げた赤牛がたくさん群れていて、教会のつりがねのようににぎやかである。牛つかいの老人が犬をつれ杖をもっている。犬は毛が長くて暑そうである。途ですれちがう子供たちはみな手をあげてあいさつする。彼らの上に幸あれ。十二時ごろ樅の木荘の前にかえってくる。昨日の青野にまたすわって、しばらくすると黒い雲が出てくる。ひるめし後、夕立がきて雷がなる。その雨がそのままつづく。部屋の中でベッドに寝転んでNに借りてきた Imitatio Christi を読んでいる。そのうちにねてしまう。夜、雨がやんだので、太陽館にビールを飲みに出かける。日本に捕りょになって四年いたというおじいさんに会う。彼、コンバンワ、イカガデスカなどという。
7月17日
天気よい。青年宿泊所のところから森に入ると、昨日の雨で森がにおいたっている。空気がまだしめり気をふくんでいるので、宿泊所で若者たちの吹く口笛がどこまでもとどいてくる。ウェッサー村の谷を越えて馬の種つけ場まで行ってみる。ひろい青野が南に開けていて、きのう路で会った牛の群が向う側でベルの音をなりひびかせている毛なが犬が走りまわっている。ひるから水浴場の方へ行く。今日は保養公園で音楽があるので、その辺に人が群れている。そこから青野をつっきって野の上の端にある水浴場にくる。少しばかりエロス的な気もちが動いて、裸の人たちをみたかったのである。といっても、きわめて自然無邪気な、さわやかな気持にすぎない。それから森をぬって下りて来て、保養公園で音楽を聞く。曲の間に、人人はやはり音楽会のフォアイエのように池のまわりを半分気どって、ぐるぐるまわっている。夜また太陽館でビールをのむ。日曜なので村の人々くる。酔ってうちに帰り部屋にいると、主人が、いまみんなでブドウ酒をのんでいるから一しょにどうだとさそいにくる。ビールで酔っているので辞退してベッドに入る。となりの部屋で二時ごろまでギターをならして歌をうたっているのがきこえる。一つはたしかに、メンデルスゾーンの猟人の歌のように思えた。また何か森の陽のあたるところにある一つのベンチを讃美した歌の文句が夢うつつにきこえるように思えた。
7月18日
フインステルベルクまで散歩する。山は九百メートルほどの高さで、テューリンゲン一帯の森林地帯が見わたせる。帰りみち、また牛の群にあう。牛の首につけたベルの音は決してでたらめでないことに気がついた。ちゃんと三度と五度の和音になっている。但し大ぜいの牛の中に二、三匹は、かみくず屋のベルをつけて調子をはづしているのがいる。夜ははやくねる。
7月26日
天気が良く、陽が強いので日なたは大変に暑い。牧草地の青野でひなたぼっこをする。エーレンフェストの統計力学の本をそこで読む。夕ぐれ、向うの土手でクラリネットの音がきこえる。何かの曲を練習するとみえて、同じせんりつをたどたどしく何度もくりかえす。息が弱くたえだえとしている。
Pubertät (管理人注・思春期)の少年の声のようであわれはかない。星が出て金星のつのが見えるような気がする。空気がすんでいるのでよく見えるのか、或はこちらの錯覚か。それから谷川の上の青野と森の境の方に行く。森のがわには、ひるまのほこりが残っていて、青野の方のがわの空気はつめたい。
(カットは筆者自身による「野球を見る人」)
第16回 第400(1963/11/10)号
7月28日
天気はやわらかに、雲がちぎれて天にある。ウェッサー村の谷をのぼって谷河の源までいく。それからアイゼンベルクくろがね山の山腹をからんでもどってくる。草いきれと、木の切りかぶのやにのにおいで、むれるような路である。ひるから、うしろの高みの青野にいて、芭蕉の奥のほそみちを読んでいる。針もみの林に風の声がしている。下の方から子供の声などを風が送ってくる。子供たちは針もみの林の中でハイデルベーレ(管理人注・こけももの一種)をとっているのである。四時近くに帰ってくる。路にほこりがたってまっ白い。林のところで、子供らはまだハイデルベーレをとって、口を紫色にしている。
夕食後散歩に出ると、風がすっかりおちて、ガラス炉の煙が空中に澱んだままなびいている。森を通り抜け太陽館に行ってビールを飲み、そこで、商業中学に行っているという息子と十一ぐらいの娘をつれたおやじさんと知り合いになる。十一時ごろ外に出ると、星が一ぱい出ている。北斗が日本でみるより大分高いことがわかる。空気が冷めたく、からだがふるえる。ガラス炉にまっかに火がもえているのが工場の窓から見える。夜中に目がさめて一種の妙な気もちになる。心臓を早くもおそくも止めることが出来るような、自分のいのちを手の中にもっていて自由にできるような感じである。外をまだ時々自動車が走りすぎるから、そうおそくないと思って時計を見ると一時である。
8月1日
今日午後の汽車で僕も引上げることにする。その前に、十一時の汽車でシュロイジンゲンという二駅ばかりさきの小さな町に行く。
駅でハンスのお母さんが切符買いに来ている。多分、夕方六時の汽車で一しょになると思う。シュロイジンゲンは、古い小さいきれいな町である。まん中に小高い丘があり、城がある。白い石と桃色の石でできた明るい、城であって、そのうしろに教会と広場がある。
広場には、型の如く議事堂と噴水、それはここヘンネベルクの太守の奥方エリザベートの丸ぽちゃの立像で愛すべき姿が上にあって、その下の台の四方に子供の顔がついていて、その子供が口をふくらして水を糸にふいているのである。
ひるめしを城の前のはたご御料理屋で食う。前が城門につづく広場で、四辻で、いろいろ交通がある。自転車旅行の少年が二組、一方は暑いのに日にやけた上半身をはだかで、さわやかなかっこうで食事している。他の一方はサイダーを注文して、弁当を食っている。その他、オートバイ旅行の夫婦や、子供づれの見物客などが食事をしている。さて、三時すぎの汽車にのって、四時にシュミーデフェルトにもどってくる。ハンスとディータ、お母さんとおばあさんがホームにいる。手まねきをして彼らがのってくる。汽車の中でディータは、丁度背の高さが窓わくに口がつく位なので、窓わくを口でなめては何度も母おやにしかられている。ハンスは母おや似である。ハンスの目はガラスのように青い。ハンケチで鼠を跳ばすこつをすぐおぼえたが、ディータはできない。鼠を一生懸命なでながらキスなどしても跳ばない。エヤフルトで彼ら一族と別れる。
第17回 第402(1963/12/10)号
8月2日
妹から手紙。日支戦争について大ぶん悲観的なことがかいてある。その他、うちのこと絢々と。そして私の手紙はどうせはすかいにしか読まないでしょうけれど、などとかいてある。はすかいどころか、何べんでも読む。
8月9日
たいくつで仕方がないくせに勉強する気が少しもしない。レクラムに借りた甘い甘い小説、Bitte,bitte,heirate mich (管理人注・「どうか私と結婚してください」の意)というのを読んでいる。日本では戦争が続いているのに、ここではソファでたいくつしている。実に自らはじ入る次第である。
8月15日
ひる前公園に行く。日はあついけれど風が秋めいている。ふと、どこかで蝉がないている錯覚をおこす。ベンチで読む。向うのベンチにも本を読んでいる若者がいるから、何を読んでいるのか帰りがけにそっとのぞくと、さし絵が目について、それは南洋かビルマあたりのことをかいたものらしく、そういう風俗の女の絵がついていた。ドイツの青年は、南の未開の国に一種のあこがれをもっているらしい。ドイツロマン主義の名ごりか。ぼくも恥かしながらこの気持に同感する。夜は赤毛嬢に日本語を教えてやったお礼の招待で、ラーッケラーでブドウ酒をのむ。したたか酔って、うちへ帰ってからヘドをはく。
8月17日
朝、風がひゅうひゅう音をたてている。つめたく空が灰色に曇って、向うの裁判所のドームの所だけ一ところ雲がやぶれて深い青い色が見える。時にしぐれて、バルコンの上のガラス屋根をたたく音、バルコンの手すりに張ったトタンをたたく音は日本の雨の音を思わせる。丁度二百十日の前兆のような具合だ。アスターの花がテーブルに出ているのは秋が来た証拠だ。夜ゴーリスの城へセレナーデをききに行く。ロココ式の城の二階にあかりがついていて、そこに音楽をやる人々がいる。われらは庭のとちの木の下でそれをきく。しぐれが降りだしたために庭の芝生がぬれて葉末に光をうつしている。弦楽、男声合唱、混声合唱、少年合唱などである。音楽をきいているときに、風が遠くから渡ってきて、木末から露をふきおとし、遠方の鐘の音をはこんでくる。少年合唱のフルート伴奏つきの民謡は、哀愁と憧憬のまじった追憶の甘さだ。「子もり歌」「タネの集まりの歌」のときには、空が晴れて星が出てくる。最後はモーツアルトの「夜曲」で終る。
9月12日
雨ふり暗い天気。夜よくねられない。少し物理を考えるが、だめだ。そこで雨の中を外に出る。さて公園のベンチにしばらく腰をかけている。雲がひくくたれこめて、エルスター川の白い水面を残してあたりはけぶり、暗く、寒く、万物みなぬれている。
9月13日
党大会でのヒットラーの演説をかいた新聞をもって公園のベンチで読んでいると、黄色い木の葉がおちてくる。チェコと戦争が始りはしないだろうかと、ハイムの学生たちは心配している。彼らは戦争になれば兵隊にとられる。
第18回 第404(1964/1/25)号
9月15日
朝から寒く霧雨がふっている。物理をこねくるが一向うまくいかない。夕方までこねくって公園に行く。寒空が灰色で少し夕やけの黄色がそれにうつり、白樺の木立がうすやみに浮いて見える。目がつかれていて景色がぼんやりする。空気がつめたく鼻がいたい。うちへ帰って鼻血が出た。ばんめし後また物理をこねくってついにやめてねる。因果な商売だ。チェコは大動員して、国境の町は兵隊と自動車で身動きもならぬぐらいだそうだ。
9月17日
考えごとはうまくいかない。夕方、あきて散歩に行く。公演を通りすぎて小チョッハー村の方に行き、少年団のキャンプ場の方に行く。ベンチに腰かけていると、うしろの大きなかしわの木からドングリがぽつんぽつんとおちて土をたたき、見ている間にそれが十ばかりになる。これを拾ってポケットに入れてもち帰る。途中で六時の鐘が方々の教会からひびきわたる。夜めしのあと、ドングリでコマを作って食たくの上でくるくるまわしっこをしてドイツ人学生たちと遊ぶ。
9月18日
ひさしぶりで上天気であたたかく風がさわやかに、また夏がもどってきた。そこで散歩に出かける。エルスター川にはボートをこぐ若者が多い。あたたかいので、夫々裸体または軽装して肉体を日にやいている。小メツセの遊園地に行く人が向う岸をぞろぞろ行く。子どもが楽しそうに前へ行く。母おやがうしろに来る。川の上に岸近く一そうのボートがあって、その中に半裸の若者が日にやけた脚をひざ立て、組んだうでの上にあおむけに顔をのせて、空を見ながら舟を流れにまかせている。一人でそうしているのかと思ったら、彼の脚の間に彼の腹をまくらにして、もう一人の少女があおむけになっている。これは甚だ目をひく光景である。エロス的であって、しかし決してみにくくはない。帰るときいささかつかれて、また鼻血がでる。バルコンに出ると今日は競馬があって、川の向うの競馬場からの音楽を風が流してくる。その音楽が周期的に大変近く聞える。夜へやで昼のエロス的光景を反すうしていると少しばかり物がなしくエロス的感がいが起ってくる。
9月19日
同宿のドイツ人学生たちは口ではいわないが、戦争になることを心配しているそぶりがしきりと見える。夜、食堂でラジオをききながらヘルメッケのおばさんは針箱を出してくつ下をつぎ、兵隊から休暇で帰ってきた学生ヴインターは制服の皮おびをみがいている。つばをふっとたらして靴ずみをつけてこすっている。夜は静かだ。
第19回 第406(1964/2/25)号
9月21日
朝から物理。ちょっと五、六校のところで、たちまち行きづまる。今日は人間が恋しくてしかたがない。夜、インド人ディッタが来たから一しょに映画へ行く。
9月28日
夜、学生ハイムの一同を日本から来たMドクトルがおごると言い、エンテプラーテンを食べ、ブドウ酒をのみ、次に席を食堂から広間にうつしビールを飲む。はじめはテーブルをかこんでいたが、やがて例によって日本式がよいと、テーブルをどけ、床の上にクッションを持って来てすわり、ねころがったりする。そしてビールがからっぽになると、クッションの投げ合いをする。ヴインター・レクラム・ミュラーはごきげんになって、僕をじゅうたんでぐるぐるまきにしてしまう。僕が動かないでいると、レクラムがトモさんが死んだという。ボーマンさんがトモさんのおとむらいだといって、ローソクを持ってきて、ラテン語のお経をよむ。僕の口の中はじゅうたんのごみでじゃりじゃりになる。ヘルメッケおばさんはいやはやあきれたという顔で苦笑しているし、小間使いの女の子イレーネは、きゃあ、きゃあいう。
9月29日
ラジオで日本の宇垣外相がやめたというニュースをきく。こちらもチェコあたりで風雲があやしいが、日本でも何かおこりはしないか。
9月30日
ミュンヘンでムッソリーニ、チェンバレン、ダラディエ、ヒットラーの会談が昨日あり、その結果が発表された。ドイツはズデーテンをチェコから分離したという。これで戦争の心配は遠のいたが、弱い国はあわれだ。七百万人のチェコ人はこれから苦しむにちがいない。
10月15日
今日はハイムの小間使イレーネのたん生日につき、おくりものの買いものをする。夜、ベルン氏という日本人と結婚した老夫妻の家によばれる。クセという、日独混血のむすめさんもよばれている。みな、思い出の中だけで生きているような、さみしそうな人ばかりだ。夜ふけて一時ころとなる。クセを家までおくっていくと二時ごろになり、もう帰りの電車はない。郊外なのでタクシーもない。しかたなく歩いて帰る。そうすると三時ごろになる。それでも路に人通りはある。が、みんなよっぱらいばかりだ。
10月16日
このごろは心がかなしくていけない。気をはらそうと思って、カピトルでアジアたんけんの映画をみる。ペルシア、トルキスタンからインドに入り、ヒマラヤを越えてゴビの砂漠に出てモウコから北京へ出る。アジアは偉大な大陸だ。
帰って物理の本を見ている。よくわからない。そのうち心の中が黄疸のように重苦しくなってくる。自然はなぜ、もっと直さい明瞭でないのだろうか。
10月18日
N、このごろしょっちゅうせきをしていると思っていたら、肺に異常があることがわかり、入院する。但し、二、三日、診断をうけるためだという。
10月25日
久しぶりに学校へ出る。昨日論文の別ずりが来たので、これをきっかけにして出る。中国人ワン君に会う。彼も仕事がうまくいかないとこぼしている。ハイゼンベルクはコペンハーゲンに行っている由。オイラーは僕の仕事面白いといってほめてくれるが、こちらは一向そう思えない。バッゲには、論文のドイツ語訳を見てもらったのでお礼に日本の本を送る。
11月16日
今日はざんげ日でやすみ。この日はいつも雨がふるというが、今日もくらく、いんうつで雨がふっている。前のひろばは一面街路樹の葉がちりしいていて、それがぬれて路にはりついている。こんどは考えかえて、B線の理論を少しやろうと机の前にすわっている。すわっているだけで少しもはかどらない。同じところを考えがぐるぐるまわって、休むに似ている。一日机にすわっているので、ヘルメッケ小母さんなどは実に勉強をよくすると感心しているが、すわっていることと、勉強していることは別だ。先日からまた学校は怠けつづけている。今週は一日も出ない。これでは困る。
11月17日
朝からいんうつな天気。湯川、坂田、小林、武谷の共同論文送ってくる。彼等ははりきっているのに、こちらはドイツまで来てくさっている。ひるから渡辺君来て、学校へちっとも来ないが病気ではないかという。
第20回 第407(1964/3/25)号
11月22日
仕事の行きづまりをうったえて、少しばかり泣きごとを仁科先生に書いたのに、先生から朝がたに返事がきた。センチだけれども、読んでなみだが出てきた。
いわく、業績があがると否とは運です。先が見えない岐路に立っているのが吾々です。それが先へ行って大きな差ができたところで、あまり気にする必要はないと思います。またそのうちに運が向いてくれば当ることもあるでしょう。小生はいつでもそんな気で当てに出来ないことを当てにして日をすごしています。ともかくも気を長くして健康に注意して、せいぜい運がやって来るように努力するほかはありません。うんぬん。これを読んでなみだが出たのである。学校へ行く路でも、この文句を思い出すごとに涙が出たのである。
11月23日
ゆうべはねどこに入ってから、いろいろなことが頭にうかんで困った。涙もろい弱々しい考えばかりである。自分ひとりとりのこされて人々がみな進んでいるような気もちである。さてそんなことで、すいみん不足で、朝起きて、はみがきようじに、はみがきとまちがえてポマードをつけたりした。ひるから久しぶりに公園に散歩に行くと、もうすっかり冬だ。
T夫妻がぼくに早く結婚しろという。ぼくがこのごろゆううつそうな顔をしているので、こういう処方せんをくれたらしい。
12月6日
もう十二月で、クリスマスの気分になってきた。朝、靴をはこうと思うと、靴の中に Gruß von Nikolaus (管理人注・サンタの贈り物)と書いた紙きれが入っていてチョコレートが入っている。ヘルメッケ小母さんのしわざだ。
12月9日
どうも日記を書くのがおっくうになってきた。書けばとにかく泣きごとになるからだ。学問とか芸術とかいう崇高なものに反撥心が起っていけない。
12月12日
ハイゼンベルクと相談して、B線の理論をやっている。というのは、湯川理論では中間子の寿命があまり短かすぎて実験値の五万分の一としかならないことがわかったからだ。
12月14日
計算を進めたら積分が発散した。こういうことをやっていたのだ。中間子が直接に電子と中性微子にこわれずに、中間子は一度陽子と中性子になり、それが電子と中性微子こわれると考えようというのだ。ところが中間状態の陽子中性子の状態がやたらにたくさんあって、積分が発散してしまうのである。
ひるから散歩に行く。空気が渋いようにつめたく、ヨハナ公園の池が半分凍って、あひるが凍っていないところに泳いでいる。鳥がたくさんむれている。花壇は樅の葉で霜よけしてある。公園をあるいていると、中性子だの中性微子だのそんなものどうでもよいという気がして来るから困る。
Nはあれからサナトリウムに行ったが、腹痛を起し、懐炉を送ってくれなどといってきた。少々心細げで心配していたが、今日ははがきが来て、だんだんよくなっている由。
12月27日
寒波のため、ゆうべはあれからマイナス十度まで下がったという話だ。朝おきると、僕のひと晩の息がすっかり凍りついて美しい模様を作っている。
夜はトーマス教会にクリスマスオラトリウムをききに行く。もうじきクリスマスで、そして一九三八年が終りになる。
第21回 第409(1964/4/25)号
1939年
1月6日
夕食後新聞を見ていると「雪の中の死」という記事が目についた。読むと若いインドの学生ラム・ディッタ(廿四才)がジルベスター(管理人注・大晦日)の夜、オーベルウィーゼンタールの雪の中でこごえ死んだ、と書いてある。いそいで外人学生事務所に出かける。きくと、やはり、あのディッタだそうだ。ディッタは学校でも僕以外には話相手もなくいつも孤独であった。そのディッタが、雪の中にころがって目をつぶっているありさまが頭に浮んできて、もって行きどころのない気持がして何も手につかないから、そのままねてしまおうと、ねどこに入ったが、ねむりに入ろうとするごとに、ディッタということばが出てくる。彼を殺したのは白人たちだなどという想念が頭にしつこくこびりついてくる。彼はおそらく勉強のつかれを癒そうと森に出かけたのだろう。そして、にぎやかに人々のさわぐジルベスターの夜を自分も一しょに楽しもうと山荘に出かけたのだろう。だがやはり、白人たちの仲間に入れず、一人で雪の路を帰って行ったのだろう。そして寒さになれないからだで路にまよい、つかれはてて森に住む動物のように、木立の下、やぶの中で死んだのだろう。何かインドのやさしい人たちが、がむしゃらな白人たちにうち負かされた縮図をみるような気がして、いつまでもねつかれない。
1月9日
久しぶりで雪の中を散歩に歩く。雪がとけて路は、ぐしゃぐしゃしている。小児遊園地から公園もぬけて、トーマス学校のところを通る。雪が凍ったのがとけて路がぬれている。その上に犬の糞がある。そんなものを見て歩いている。なぜ犬の糞は下らないというのか。そうして学問とか芸術とかはなぜ下らなくないのか。など変な考え方がぐるぐるまわる。
夜、めしもうまくない。レクラムがめしのあとで、トモサンよ、という。トモサンよ、きみはディックが死んでショックを受けているようだ。ディックが死んで気が沈む気もちはわかるが、きみも大事なからだだ。あまりくよくよしないで元気を出せ、という。
1月19日
うちで仕事を少しはじめる。天気よく鳥の声が聞えている。さてWが来て、一昨日、ゼミナールでベルリンから来たらイツェッカーが面白い話をしたという。ウランに中性子をぶつけると、ウランがまっ二つに割れて、バリウムとかストロンチウムとかができるということを、ベルリンのハーンが見つけたという話。僕が怠けている間にこんなニュースが入った。そこで怠けたことに気がとがめてくる。
1月25日
朝からうす暗い、いんうつな天気で、また寒くなった。一日計算のみ、自己場を算出して引こうと思う。さてこのごろ少し消耗しているとみえてヘルメッケおばさんが心配して、卵をもってきてくれたり、牛乳をくれたりする。少し日にあたりなさい、顔色が悪いからなどという。しかしどこに太陽がある、というと、それは今日は天気が悪いから仕方がないが、という。ほんとに今日はうす暗い。
夜、タキシードを着て、ゲヴァントハウスに行く。第五シンフォニーと、トーマス教会の少年合唱があるはず。OとT夫妻といっしょ。
1月26日
ゆうべの音楽のせいか、少し心がはずんでいる。ゆうべは音楽がすんだあと、ハンネス亭でビールをのみ、一時ごろになる。学生ハイムに帰ると鍵を忘れていて入れない。そこでOの下宿でとめてもらう。朝おきたのが十一時。それからOと二人で詩集など読んでいる。ちがった場所で寝たので、旅行にいったような気が少しする。帰ったのがひるすぎで、ハイムではみんな、トモサンや、どこへ行っていた、と訊く。
第22回 第410(1964/5/10)号
2月6日
先日、小間使の女の子イレーネが血をはいた。医者にみてもらったら結核だというので、今日、病院に入ることになった。出て行くのを玄関で送って、それから、広間の出窓から下の通りをみていると、ヘルメッケおばさんと二人で行く。イレーネは小さい赤かばんを肩にかけて、顔が紙のように白くみえる。路に黒い犬がいるのを、イレーネは通りすがりにしゃがんでなでたりしている。そして向うの角をまがって行った。Nくんがよくせきをしていたので、Nくんからうつったのではないかと心配している。
2月7日
Nくんからハガキ来る。ゆっくりながら順調のよし。
2月9日
天気よく暖かいから窓をあけておくと、鳥の声や教会の鐘の音が入ってくる。教会の塔が日にきらきら光っている。
仕事はうまくいかない。何が何だかわからなくなった。ひるからくらくなって来て雨となる。なまぬるい、しめっぽい風が吹いて来る。W夫妻のところへ行く。帰りは日がとっぷりくれてやみになる。そのくらやみの中で雨がさあっと風といっしょに降っていて、風が耳もとを音をたてて過ぎていって、路ばたの生垣がさあさあと鳴っている。電車ののるのがいやで、どこまでもそのくらやみの中を歩いて行く。
2月14日
変りなし。ゼミナールに行く。バッヂが、ヘヤ・トモナガはあまりに勉強しすぎる、という。そんなに見えるかしら。困ったことだと思う。
2月16日
朝から雨がしとしととふっている。仕事がうまくいかないから雨の中を公園に行った。みちがぬれている。無数の雨足が池の面を一面に白い色にして木からしずくが落ちてくる。エルター川に近い細みちを行くと、妙なものを見つけた。それは、灌木の小枝にひっかってぶらさがっている。だれかが昨夜ここで情熱をかたむけたとき使ったゴムの袋である。そこを行きすぎて半町ばかり行き、他の面の雨足を見ていると、身も心もさみしくなって、それをもう一度見たい気がしてくる。そこでひきかえしてよくよく見ると、雨にぬれて枝にじっとぶらさがっているものが、非常にこっけいに見えてくる。さて、そんなことをしているうちに帰ってくる。ひるからは、また仕事だ。
2月18日
夜は外人クラブで舞とう会。ハイムの学生たちとタキシードを着て出かける。よあけの三時まである。
第23回 第411(1964/5/25)号
2月19日
ハイムにMとイレーネと二人の結核患者が出たので、一同レントゲン検査することになり、ヴェルナーと二人で病院に行く。待っている間、ヴェルナーは神経質になって、そわそわしている。さて、レントゲン室のくらやみで二人裸になって、ドクトル、ティーメ(Nの主治医をした人)が見てくれる。ヴェルナーも僕も健康ということになる。さて、そのあと二人で町を歩く。ヴェルナーも僕も、少しほがらかな気がして、心が浮き浮きしている。しかし、おかしくあわれではないか、二人とも、実質は別に診断の前とあととで少しもちがいはないのである。
2月21日
学期最後のゼミナール。ストラスマンのウランが分裂する話。話のあとで老ホフマン教授が、近ごろさびしかったドイツの学界で、このような大きな発見がしばらくぶりにあったことは大変よろこばしい、とあいさつする。
2月22日
計算が少し進んで、自己場によって陽子の磁気能率が大たい実験と合うように出るように思えだした。
2月23日
計算をなお進めてみたら、やはりだめだ。磁気能率はこの近似ではゼロになってしまった。つくづくと情なくなる。
2月28日
暖く風なく、天気がよい。それでやし公園の方まで散歩する。海賊クラブのボートハウスのまえのやなぎの木は、もう萌え出している。川面にかすみが立ちこめて、水がにぶく日にかがやいている。白鳥が川に出ている。その泳ぐ波がきらめく。夜、ハイゼンベルクに内証で日本に帰っている夢を見た。休暇前に彼にあいさつせずに休んでしまったことに気がとがめているらしい。それとも魂がほんとにぬけ出して、昨夜日本をさまよっていたのかもしれない。
3月7日
夜、ヴェルナーと表の部屋でビールをのんでいる。ヴェルナーが、あれを見よ、というから窓の外をみると、今、前の広場の向うの屋根から満月が出かかっている。ヴェルナーが始めて酒をのんだときの話をする。ワイマールのギムナジウムに行っていたとき、ギムナジウムの中等から高等にうつる数学の試験に落第点をとり、悲観してしまって、学校の帰りに落第仲間の五、六人でブロイハウスへ行き、ビールをのんでのみまくり夕方うちへふらふら足で帰ってきた。うちへ入ると、女中が、坊ちゃま今日はお風呂に入る日です、というので、風呂場へ行き、裸になったまではおぼえているが、あとは知らない。何か寒いと思って気がつくと、風呂の中で裸でねていたが、湯はなくて、あっちに一滴、こちらに一滴、しずくがついているだけだ。そこで、あわてて時計をみると、一時間ぐらいそうしていたらしい。おかげで酔もさめて、食事のとき、だれにも見つからなかった。さて試験はそれでも高等に入るにはさしつかえなく仲間もみんな進級した、というのである。
第24回 第412(1964/6/10)号
3月8日
朝、大賀君を駅におくりに行く。ミュラー、ヴェルナー、それに新しく日本から来た学生伊藤君。大賀君はあこがれの外交官になるので胃病のことも忘れ、連日の準備でつかれ、少しやせているが元気だ。
3月27日
今日はもう三月二七日である。このごろまた、例の時間のたつのがこわくてそのためかえって何もしないという病気が起こっている。従ってその後仕事は一向にすすまず、気がめいってしかたがない。一日何もしない。
3月28日
朝めし後散歩に行く。小児遊園地をぬけエルスター川を越える。今日は雨あがりであたたかい。丁度桜の咲く前にふる雨のように、空気がにおいをもっている。エルスターをこえると、工場町の方へ行ってみようという気になってくる。気がめいっているときは、きたない町へ行きたいものだ。工場町は不規則で、映画やおどり場の所へ出たと思うと、堀があったりする。
堀にそって汽車が連結をやっているのをしばらく見ている。ここは製材所で材木のにおいがしている。坂をおりて行くと、小さい広場があり、職業紹介所らしいものがあり、仕事をもとめる人々がその前に行列して待っている。この広場の共同便所に入って、小便をする。しながら、児戯のようならくがきを見ている。それからエルスターのところに又出て、かえってくる。夜、部屋があたたかいので、裸になってソファにころがり壁のかがみをとって、裸をいろいろとうつしてみる。あわれはかない少年ナルシサスのような児戯だ。
3月30日
二月廿三日の計算の誤りなことを見出す。その間に一か月たっているのだ。バカもこうなると甚しい。
4月3日
夜、ウェルナーと二人でテューリンガー・ホフでビールをのむ。かえりに、そこの前にいつも客まちしている馬車にのって帰ってくる。ウェルナーの注文でわざとまわり路して、公園をぬけ、エルスターの所から、競馬場へ出てかえってくる。空気がつめたい。人家の所へ入ると、路で金輪ががらがら両側の家にひびく。学生ハイムの所へつくと、下からウェルナーが信号を口ぶえでふく。そうすると上からレクラムが窓を開いて口ぶえでこたえる。ハイムの学生らはよく口ぶえで合図して下から四階まで上ってくる手数をはぶいている。
4月7日
今日は、カール金曜日(管理人注・Karfreitag)で、キリストが十字にかかった日である。一日何となくものがなしい。ひるから散歩に出ようと着物をきかえたが、そのままいやになって、又着物をぬぐ。そして、広間へ行って書棚からマイエルの字引を出してメランコリというところを引いてみたりしている。
5月13日
今日はもう五月十三日だ。先日からかぜで二週間ばかりねていた。今日はじめて外へ出ると満目青々として、エルスターにはボートなどこいでいる人々がいる。
5月15日
今日久しぶりで学校へ出る。Wはぼくが病気だったとは思わず、ガリガリ勉強していたのだろうなどという。帰りみち、紙、鉛筆、ハミガキ、ハブラシを買う。気分を新たにして仕事をしようというのだ。ところが映画にはいってしまう。そして少し気がとがめながら帰ってくる。夜計算にかかる。少しすすむように思える。しかし多分また、ぬかよろこびだろう。
5月18日
昨日仕事はまた行きづまった。もうどうでもなれという気がする。朝バルコンから下を見ていると、今日は耶蘇昇天の祭日で、少女がきれいに着かざって遊んでいる。それを見、木々の芽を見、そこにさえずっている鳥を見ていると涙が出てくるのである。何とセンチメンタルなことだろう。
(注・やや唐突な印象がありますが、朝永教授は「もう提供する材料がなくなった」として、連載をここで打ち切られました。当時の新聞会の朝永氏担当二木都志子記者(1986年7月在米中にご逝去)からそのような報告があったもので、詳しいことは分かりません。「滞独日記」は1939年5月18日で終わっていますが、朝永氏はこの年、第二次大戦の開始により引き揚げ船で日本に帰国し、在独中の論文によって東京帝国大学から理学博士号を授与され、翌年ご結婚、1941年に東京文理科大学教授となられました。)
ボロ家もまた楽し
★教育大学新聞 第315(1959/1/25)号所載★
(注)これは、朝永振一郎教授が学長在任中の1959年、「教育大学新聞」に寄せられたエッセイです。なかなか味のある興味深いものなので、ここに併載しました。なお、本文中には桐花寮が「今年度中にとりこわしになる」とありますが、実際には予算獲得が出来ず、桐花寮は東京教育大学の閉学に至るまで使用されていました。管理人は在学中桐花寮生でしたが、入寮のため運送屋に荷物を運んで貰った際、運転手が「何でこんな汚いところに入るの?」などと訝しそうに私に聞いたのが印象に残っています。先輩からも「あんな毎年赤痢が出るようなところははやく出た方が良い」などと勧められたこともありましたが、私の在寮中には赤痢が出たことはありませんでした。いくら汚いといっても、当時寮費(国庫納付金)は月額100円であり、また、朝食、夕食の給食もあって、安く食事が出来るのは学生にとっては大きな魅力でした。
★
うちの大学はいま本館建設のさいちゅうで、これができると少しは立派になりそうだが、今までは日本有数のきたない大学だったと思う。少なくとも東京では最もきたない大学であった。特に桐花寮という寄宿舎は悪名高いものであって、黒沢明監督の、映画「どんぞこ」(管理人注・正しくは「どん底」です)の場面そっくりで、こういうところに住む学生はたまったものではないかもしれない。しかし、学生諸君にはお気の毒ながら見物して話のたねにするのにはなかなか乙なものであって、今年度中にとりこわしになるのが、ちょっとおしいような気もする。
むかし京都の中学校にいたとき、この学校は日本最古の中学だといって威張っていたが、そのぼろさ加減も日本最高であって、床にはいたるところに穴があり、天井は波のようにうねっていて、雨が降ると、雨が漏る、というよりも、あたかも天井裏に雨樋でもしかけてあるかのように、天井から滝がふってきた。悪童たちはよく教室の中で傘をさしてふざけたものである。高等学校に入ると、その寄宿舎がまた相当なもので、おまけに学生たちの間に部屋をきたなくする趣味が流行していたので、そのきたなさに環をかけた有様であった。
こういう環境で教育されると、どうも、あまりきれいな建物の中に入ると窮屈で、そして机の上をきちんと整理したり、身のまわりをちり一つないようにする、などということは面倒くさくておっくうだというような悪い習慣がついてくる。そんなわけで、いつかアメリカに行ったとき、あまりにもちゃんとした家にいて、雨がふっても天井で雨漏りの音一つしないのが物たりなく味気なく、ついにホームシックにかかった。
雨が漏ったか何かで天井や壁に妙なしみができていると、病気などしたとき退屈をしのぐのになかなか役に立つ。しみを見ているとそれがいろいろ不思議なけだものに見えたり、ドーミエの絵に出てくるようなグロテスクな人物の顔に見えたりする。数年まえ、ドイツに旅行したとき、フランクフルトで病気になって十日ばかり大学病院に、入院していたことがあった。この病院は空襲を受けて大ぶんいたんだ建物で壁のペンキが古くなって、そこにはいろいろと入りくんだ曲線のひびわれができていた。この曲線が、見ようによって、女の裸像に見えたりして結構たのしめたものである。
こういう具合に、ぼろ家というものはなかなかいいものだが、寒い冬、すきま風の入ってくるのが欠点である。アメリカにいたときの家のように、スチームが通っていて、洗面所ではいつでもお湯が出るというようになっていて、その上で、適当に雨が漏って、壁に模様ができている。そうしてどこからともなく便所のにおいとか、かびくさいにおいとかがほのかにただよってきて、その上に欲をいうとすきま風の入らない程度に壁がやぶれていて、そこから晩秋の夜など、こおろぎか何かが迷いこんできて、ころころとなきはじめる。こういうのが理想のすみかである。
だからといって、せっかく新しくでき上るわが大学の建物をよごしたりしようというのではない。人工的にそういうことをするのは邪道である。建物のよごれというものは、そこにいた人人のにおいが長い間にしみこんだようなもの、その建物の歴史をひそかに物語るようなものでなくてはならない。そしてそれにも限度があって、桐花寮のように赤痢の発生するような建物はいつまでも残しておくわけにはいかない。そこで学長は予算かくとくに努めなければならないし、学生諸君には、大学の建物を大事にして下さい、といわねばならぬことになる。
| 訃報・朝永振一郎氏は1979年7月8日、喉頭癌のため73歳で永眠されました。謹んで哀悼の意を表します。 |
★このページは2010年6月24日、当サイトに新規に追加したものです。
★「ボロ家もまた楽し」の部分は2010年7月12日、このページに追加したものです。
★関連ページ「朝永振一郎学長の桐花寮祭での講演」(2011年1月26日追加)もご覧下さい。
★Annotation: From a standpoint of Japanese pronunciation, writing "Shin'ichirô" may be better than "Sin-itiro" for English readers, but Mr. Tomonaga used to write his name in romanized transliteration "Sin-itiro".
戻る(Return)
▲
 (注)朝永振一郎氏(1906-1979)は京都大学の出身であるが、理化学研究所仁科研究室を経てライプチッヒ大学に留学(ハイゼンベルクに師事)、帰国後1941年に東京文理科大学の教授となられ、新制東京教育大学の発足に伴い1949年から1969年まで、東京教育大学理学部物理学科および光学研究所の教授を務められた。その間、1956年から1962年の2期6年間(1期4年間、再任2年間)にわたり、東京教育大学の学長を務められ、東京教育大学の発展のために尽力された。朝永氏が学長をされていた時代は後年教育大関係者によって「朝永時代」と呼ばれるようになり、東京教育大学がもっとも輝いていた時代、東京教育大学の黄金時代と見なされるようになった。教育大学新聞会は、学長退任直後の1962年、朝永教授に過去の「思い出ばなし」の連載企画を提案したが、教授はこれを快く引き受けられ、24回にわたって当「教育大学新聞」の紙面を飾っていただいた。当然、当会刊行の「文理科大学新聞・教育大学新聞 縮刷版」に掲載されているわけであるが、「縮刷版」をお持ちでない方にも、これを公開するのは公共の利益であると考えられるので、ここにその内容を紹介することとしたい。
(注)朝永振一郎氏(1906-1979)は京都大学の出身であるが、理化学研究所仁科研究室を経てライプチッヒ大学に留学(ハイゼンベルクに師事)、帰国後1941年に東京文理科大学の教授となられ、新制東京教育大学の発足に伴い1949年から1969年まで、東京教育大学理学部物理学科および光学研究所の教授を務められた。その間、1956年から1962年の2期6年間(1期4年間、再任2年間)にわたり、東京教育大学の学長を務められ、東京教育大学の発展のために尽力された。朝永氏が学長をされていた時代は後年教育大関係者によって「朝永時代」と呼ばれるようになり、東京教育大学がもっとも輝いていた時代、東京教育大学の黄金時代と見なされるようになった。教育大学新聞会は、学長退任直後の1962年、朝永教授に過去の「思い出ばなし」の連載企画を提案したが、教授はこれを快く引き受けられ、24回にわたって当「教育大学新聞」の紙面を飾っていただいた。当然、当会刊行の「文理科大学新聞・教育大学新聞 縮刷版」に掲載されているわけであるが、「縮刷版」をお持ちでない方にも、これを公開するのは公共の利益であると考えられるので、ここにその内容を紹介することとしたい。 第1回 第375(1962/9/10)号
第1回 第375(1962/9/10)号 こんな背景をもって入ってみた大学では、実験室はうすぎたなくほこりにまみれた古めかしい機械で、ほそぼそとやっているらしい二番せんじの実験、他方、理論の講義は無味乾燥な数式の氾濫、それを一つ一つノートにうつしとっていく退屈な作業。あんな神秘的に思われた相対論も、ここでは物理的な肉づけも、哲学的な深遠な考察も全くもたない、ただの数式のいぢくりまわしにすぎない。電子が波動性を持っているとか、マトリックス力学というような、若い、なまいきな学生の好奇心を極度にかきたてるような話は一かけらも出てこない。
こんな背景をもって入ってみた大学では、実験室はうすぎたなくほこりにまみれた古めかしい機械で、ほそぼそとやっているらしい二番せんじの実験、他方、理論の講義は無味乾燥な数式の氾濫、それを一つ一つノートにうつしとっていく退屈な作業。あんな神秘的に思われた相対論も、ここでは物理的な肉づけも、哲学的な深遠な考察も全くもたない、ただの数式のいぢくりまわしにすぎない。電子が波動性を持っているとか、マトリックス力学というような、若い、なまいきな学生の好奇心を極度にかきたてるような話は一かけらも出てこない。 大学三年生になって専門をきめるとき、身のほども知らず、量子力学の勉強をやろうと思ったのは、新しものずきという、若気のいたりからであった。実験物理を選ばなかったのは、一つは健康上の理由で、学生実験のとき、一、二時間立っていても痔のぐあいが悪くなるありさまでは、とてもだめだと思った。
大学三年生になって専門をきめるとき、身のほども知らず、量子力学の勉強をやろうと思ったのは、新しものずきという、若気のいたりからであった。実験物理を選ばなかったのは、一つは健康上の理由で、学生実験のとき、一、二時間立っていても痔のぐあいが悪くなるありさまでは、とてもだめだと思った。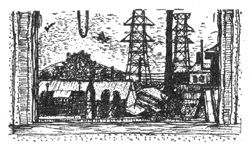 大学は何とか卒業したが、就職口もみつからぬままに、無給副手となって大学に残った。相変らず健康はすぐれず、勉強の方も何をやってよいか暗中模索状態が続いた。量子力学はその頃すでに建設が終り、いろいろな方面への応用の時代に入っていた。あらゆる物理の分野への応用が開け、毎月毎月現われる論文の数はおびただしいものであった。これら論文の洪水にまき込まれて、どちらを向いて泳いで行くべきか、ただアップアップする状態であった。湯川くんは、この洪水の中ですでに自分の進路を発見していたように見えた。すなわち、次にくるものは原子核と場の量子論であるという見通しを、そのときすでに立てていたように思われる。そして彼はこの方向に向って、着々と自分のペースで進んで行った。
大学は何とか卒業したが、就職口もみつからぬままに、無給副手となって大学に残った。相変らず健康はすぐれず、勉強の方も何をやってよいか暗中模索状態が続いた。量子力学はその頃すでに建設が終り、いろいろな方面への応用の時代に入っていた。あらゆる物理の分野への応用が開け、毎月毎月現われる論文の数はおびただしいものであった。これら論文の洪水にまき込まれて、どちらを向いて泳いで行くべきか、ただアップアップする状態であった。湯川くんは、この洪水の中ですでに自分の進路を発見していたように見えた。すなわち、次にくるものは原子核と場の量子論であるという見通しを、そのときすでに立てていたように思われる。そして彼はこの方向に向って、着々と自分のペースで進んで行った。 昭和四年ごろ、京都の物理学教室にはただ一人、その論文が外国でも引用されるような研究をしておられる先生があった。それは分光学の木村正路先生であった。先生の専門は実験で、はじめは理論物理にはあまり同情的でなく、弟子たちが理論の本などを読んでいると、時間のろう費だとおこごとを食ったという話であったが、ちょうどその頃海外視察に出かけられ、新しい量子力学が怒涛のように全世界をゆさぶっている様子を見られ、日本でも何とかしなければこの大勢から落伍してしまうことを痛感されたようであった。そのころ、長い間海外にあって量子力学の建設をその目で見、またその事業の一端をみずから担われた仁科芳雄先生が帰って来られた。そこで木村先生は仁科先生を京都大学に呼んで、若い連中に対し量子力学の講義をすることを依頼された。
昭和四年ごろ、京都の物理学教室にはただ一人、その論文が外国でも引用されるような研究をしておられる先生があった。それは分光学の木村正路先生であった。先生の専門は実験で、はじめは理論物理にはあまり同情的でなく、弟子たちが理論の本などを読んでいると、時間のろう費だとおこごとを食ったという話であったが、ちょうどその頃海外視察に出かけられ、新しい量子力学が怒涛のように全世界をゆさぶっている様子を見られ、日本でも何とかしなければこの大勢から落伍してしまうことを痛感されたようであった。そのころ、長い間海外にあって量子力学の建設をその目で見、またその事業の一端をみずから担われた仁科芳雄先生が帰って来られた。そこで木村先生は仁科先生を京都大学に呼んで、若い連中に対し量子力学の講義をすることを依頼された。 研究所の仁科研究室はまだできたてであったので、仁科先生の居室と、中はまだがらんどうの実験室一つだけが決まった部屋で、あとは暫定的なかり住まいであった。あてがわれたのは雑誌のバックナンバーや紙型をしまっておく倉庫の一角で、そこに一人で閉じこもることになった。ひる間でもときどき鼠があらわれて、黒い丸い目で不思議そうに妙な新参者をながめている。そんなところで仁科先生からあてがわれた仕事を始めることになった。
研究所の仁科研究室はまだできたてであったので、仁科先生の居室と、中はまだがらんどうの実験室一つだけが決まった部屋で、あとは暫定的なかり住まいであった。あてがわれたのは雑誌のバックナンバーや紙型をしまっておく倉庫の一角で、そこに一人で閉じこもることになった。ひる間でもときどき鼠があらわれて、黒い丸い目で不思議そうに妙な新参者をながめている。そんなところで仁科先生からあてがわれた仕事を始めることになった。 夏休みのあいだにいよいよ正式就職の決心をつけて、九月にはまた「御旅館平和館」にもどってきた。初任給六十円、それで下宿代そのほかの費用を差引いてじゅうぶん余るという結構な身分になった。神田の学生街で型の如くセザンヌやゴッホの複製を買ったり、露店で観葉植物をもとめたりして、まず平和館の小部屋を少しは人間のすみからしくととのえ、またワイシャツやネクタイなども一応とりそろえて、人なみのおしゃれもすることにした。
夏休みのあいだにいよいよ正式就職の決心をつけて、九月にはまた「御旅館平和館」にもどってきた。初任給六十円、それで下宿代そのほかの費用を差引いてじゅうぶん余るという結構な身分になった。神田の学生街で型の如くセザンヌやゴッホの複製を買ったり、露店で観葉植物をもとめたりして、まず平和館の小部屋を少しは人間のすみからしくととのえ、またワイシャツやネクタイなども一応とりそろえて、人なみのおしゃれもすることにした。 仁科研究室ができた昭和六年から七、八年にかけて、原子核物理では次々といろいろ重要な発見があった。陽電子とか中性子とかいう新しい素粒子がみつかったり、粒子加速装置を使って原子核破壊をする実験がはじめて成功したりした。また、今まで雲をつかむようだった宇宙線の本体も、次から次へと見つかった珍しい現象から急に明かになってきた。
仁科研究室ができた昭和六年から七、八年にかけて、原子核物理では次々といろいろ重要な発見があった。陽電子とか中性子とかいう新しい素粒子がみつかったり、粒子加速装置を使って原子核破壊をする実験がはじめて成功したりした。また、今まで雲をつかむようだった宇宙線の本体も、次から次へと見つかった珍しい現象から急に明かになってきた。 昭和十年ごろから理化学研究所のようすが少しずつ変ってきた。いろいろな発見から物理学が原子の世界から原子核の世界に入りこんできて、研究所でもそれに応じた再編成が必要となりつつあった。物理学の中心はそれまで分光学とかX線の研究にあって、研究所でもこの課題にとりくむ研究室が多かったが、それらの研究室の中からも原子核物理の方に転向を望む声が出てきた。そういうわけで、研究所体制をある程度修正する必要が起ってきた。
昭和十年ごろから理化学研究所のようすが少しずつ変ってきた。いろいろな発見から物理学が原子の世界から原子核の世界に入りこんできて、研究所でもそれに応じた再編成が必要となりつつあった。物理学の中心はそれまで分光学とかX線の研究にあって、研究所でもこの課題にとりくむ研究室が多かったが、それらの研究室の中からも原子核物理の方に転向を望む声が出てきた。そういうわけで、研究所体制をある程度修正する必要が起ってきた。 さて、仁科研究室もだんだん大きくなると古き良き時代も少しづつごたごたしてくる。人間関係も複雑になり、研究室の中に不平不満の空気がただようこともあった。「原子核物理ことはじめ」の時期には、いろいろ困難があっても、夜がしらじらとあけはじめるあけぼのの楽しさがあった。それから小さいサイクロトロンという機械をみんなで作り上げ、それが運転しだしたとき、みんなは将来への期待に胸をふくらませた。しかし仁科先生の野心はこれでおさまらず、もっと大きい、当時にしては世界最大の機械を新しく作る計画がでてきた。この仕事は困難を極め、実験の連中の苦労はなみたいていのものではなかった。あとでわかったことだがこの機械の設計には重大な誤りがあったのだが、それがわかるまで、実験の連中がいくら努力してもうまくいかない。さすがの仁科先生もいくらかあせりがあったようで、それが実験の場に微妙に反映し、こんな困難な仕事に時間をつぶし、何の成果もあがらぬより、もっと容易な道で研究を進める方が賢明ではないかという意見の者も出てくる。こんな考えで仁科先生のもとから離れていった者も二、三人はいた。
さて、仁科研究室もだんだん大きくなると古き良き時代も少しづつごたごたしてくる。人間関係も複雑になり、研究室の中に不平不満の空気がただようこともあった。「原子核物理ことはじめ」の時期には、いろいろ困難があっても、夜がしらじらとあけはじめるあけぼのの楽しさがあった。それから小さいサイクロトロンという機械をみんなで作り上げ、それが運転しだしたとき、みんなは将来への期待に胸をふくらませた。しかし仁科先生の野心はこれでおさまらず、もっと大きい、当時にしては世界最大の機械を新しく作る計画がでてきた。この仕事は困難を極め、実験の連中の苦労はなみたいていのものではなかった。あとでわかったことだがこの機械の設計には重大な誤りがあったのだが、それがわかるまで、実験の連中がいくら努力してもうまくいかない。さすがの仁科先生もいくらかあせりがあったようで、それが実験の場に微妙に反映し、こんな困難な仕事に時間をつぶし、何の成果もあがらぬより、もっと容易な道で研究を進める方が賢明ではないかという意見の者も出てくる。こんな考えで仁科先生のもとから離れていった者も二、三人はいた。 4月9日
4月9日 7月16日
7月16日